FP3級学科解説-2022年5月・問31~40
(31)
毎年一定金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、( )である。
| 1. | 減債基金係数 |
| 2. | 資本回収係数 |
| 3. | 年金終価係数 |
正解:3
積立型運用の将来の金額を求める際に使う係数は、年金終価係数です。
(32)
公的介護保険の第( ① )被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ② )以上65歳未満の医療保険加入者である。
| 1. | ① 1号 ② 40歳 |
| 2. | ① 2号 ② 40歳 |
| 3. | ① 2号 ② 60歳 |
正解:2
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。
(33)
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の( ① )相当額であるが、その額が( ② )を超える場合の支給額は、( ② )となる。
| 1. | ① 10% ② 10万円 |
| 2. | ① 20% ② 10万円 |
| 3. | ① 20% ② 20万円 |
正解:2
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練経費の20%相当額で最高10万円です。
(34)
子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( )に相当する額である。
| 1. | 0.75倍 |
| 2. | 1.25倍 |
| 3. | 1.75倍 |
正解:2
障害基礎年金の額は、障害等級2級の人に支払われるものは「老齢基礎年金の満額+子の加算額」の算式により計算され、障害等級1級の人に支払われるものは「老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額」の算式により計算されます。
(35)
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)の融資金利は( ① )であり、借入れをする際には、保証人が( ② )である。
| 1. | ① 固定金利 ② 不要 |
| 2. | ① 固定金利 ② 必要 |
| 3. | ① 変動金利 ② 必要 |
正解:1
フラット35の融資金利は、全期間固定金利で、保証人や保証料は不要です。
(36)
生命保険会社が( )を引き下げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は高くなる。
| 1. | 予定利率 |
| 2. | 予定死亡率 |
| 3. | 予定事業費率 |
正解:1
予定利率を引き下げると、保険金などの原資を準備するために、以前よりたくさんの保険料を集める必要が生じますから、予定利率の引き下げは保険料の上昇要因です。
(37)
契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、( ① )の年齢に応じた保険料率により算出され、転換時において告知等をする必要が( ② )。
| 1. | ① 転換前契約の加入時 ② ない |
| 2. | ① 転換時 ② ない |
| 3. | ① 転換時 ② ある |
正解:3
保険契約の転換は再契約のようなものですから、保険料は転換時の年齢に応じて再計算され、転換をするためには告知などをする必要があります。
(38)
スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険として、( )がある。
| 1. | 生産物賠償責任保険(PL保険) |
| 2. | 請負業者賠償責任保険 |
| 3. | 施設所有(管理)者賠償責任保険 |
正解:1
第三者に引き渡した物や製品、業務の結果に起因して賠償責任を負った場合に備える保険は、生産物賠償責任保険(PL保険)です。
(39)
個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
| 1. | 自宅のベランダから誤って植木鉢を落として駐車中の自動車を傷付けてしまい |
| 2. | 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい |
| 3. | 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい |
正解:3
個人賠償責任保険は、日常生活における様々な賠償事故に備える保険ですが、業務中に発生した賠償事故を補償するものではありません。
(40)
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
| 1. | ① 5万円 ② 全額 |
| 2. | ① 5万円 ② 2分の1相当額 |
| 3. | ① 10万円 ② 2分の1相当額 |
正解:1
地震保険料控除の額は、所得税においては、支払った保険料の全額で最高50,000円まで、住民税においては、支払った保険料の半額で最高25,000円までです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |


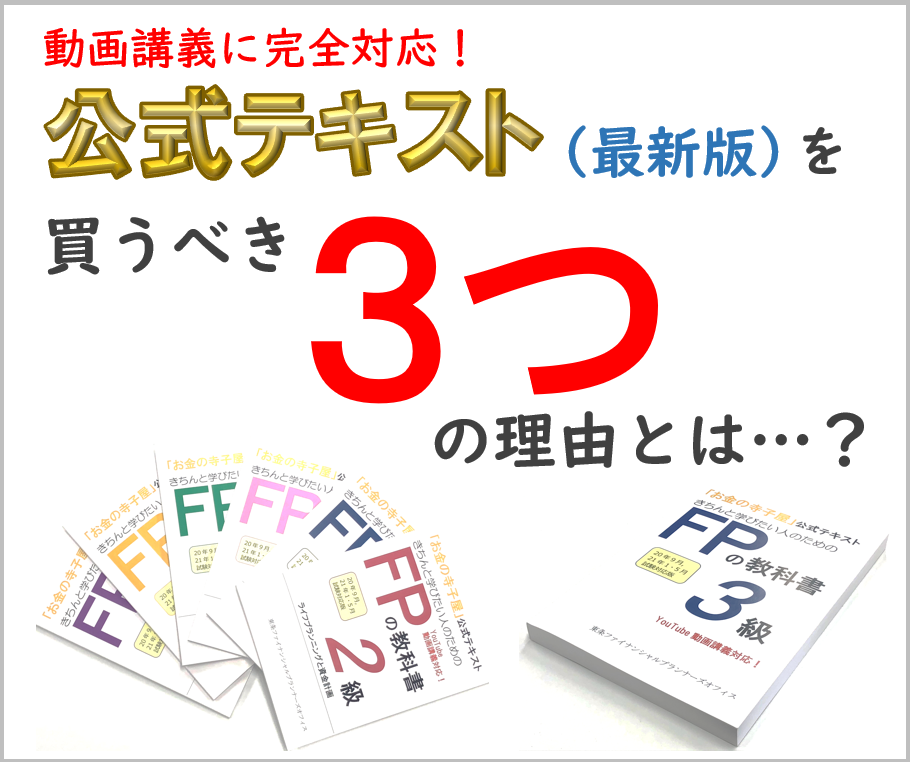
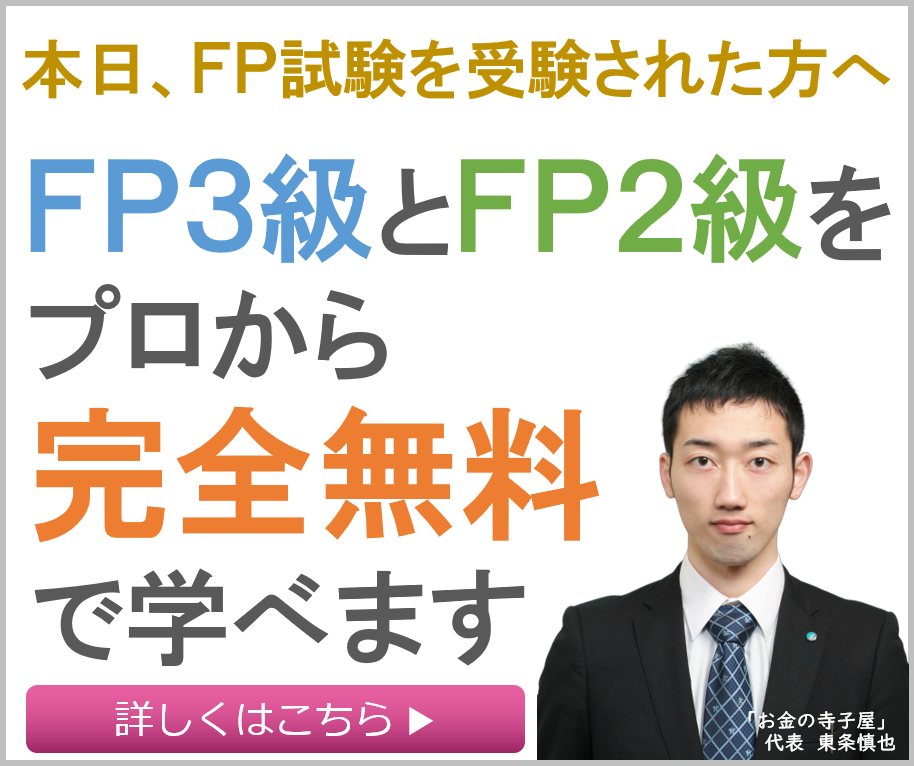
square.png)