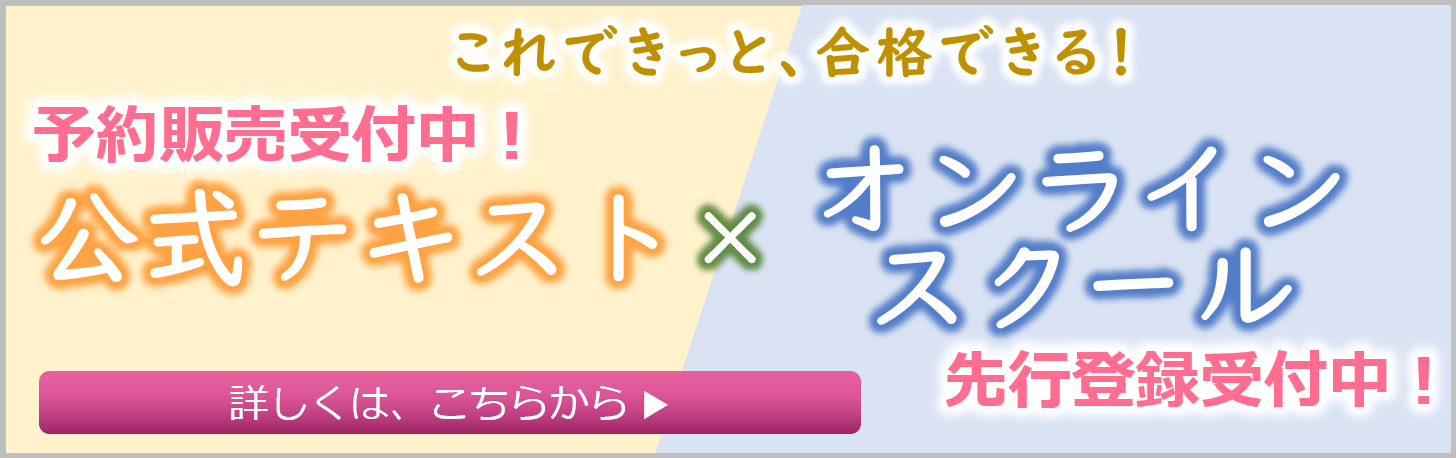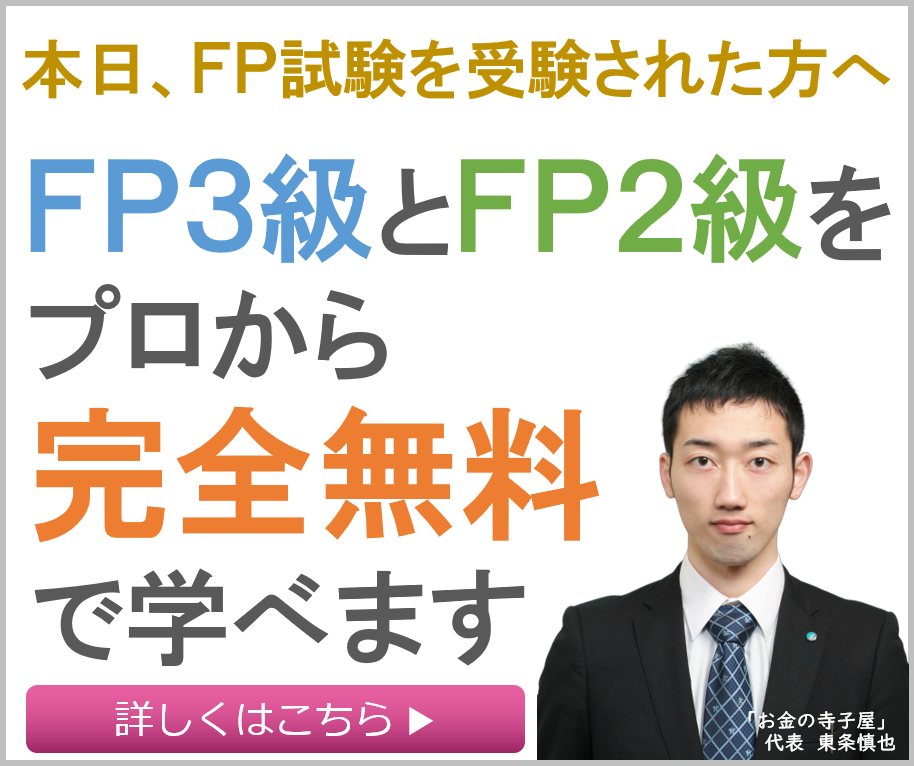FP2級実技(FP協会)解説-2023年9月・問28~34
【問28】~【問34】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
長岡京介さんは、民間企業に勤務する会社員である。京介さんと妻の秋穂さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある五十嵐さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。
長岡京介さんは、民間企業に勤務する会社員である。京介さんと妻の秋穂さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある五十嵐さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。
<家族構成>
[長岡 京介(本人)]
生年月日:1978年6月22日(45歳)
会社員(正社員)
[長岡 秋穂(妻)]
生年月日:1979年4月5日(44歳)
会社員(正社員)
[長岡 翔太(長男)]
生年月日:2006年8月18日(17歳)
高校生
<収入金額(2022年)>
[京介さん]
給与収入450万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
[秋穂さん]
給与収入400万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
<金融資産(時価)>
[義博さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
銀行預金(定期預金):150万円
投資信託:50万円
[由紀恵さん名義]
銀行預金(普通預金):100万円
個人向け国債(変動10年):50万円
[住宅ローン]
契約者:京介さん
借入先:LA銀行
借入時期:2013年12月(居住開始時期:2013年12月)
借入金額:2,200万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:固定金利選択型10年(年3.00%)
返済期間:25年間
契約者:京介さん
借入先:LA銀行
借入時期:2013年12月(居住開始時期:2013年12月)
借入金額:2,200万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:固定金利選択型10年(年3.00%)
返済期間:25年間
<保険>
[定期保険A]
保険金額3,000万円(リビング・ニーズ特約付き)。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は京介さん、保険金受取人は秋穂さんである。保険期間は25年。
[火災保険B]
保険金額1,400万円。地震保険付帯。保険の目的は自宅建物。保険契約者(保険料負担者)および保険金受取人は京介さんである。
【問28】
京介さんは、現在居住している自宅の住宅ローンの繰上げ返済を検討しており、FPの五十嵐さんに質問をした。京介さんが住宅ローンを120回返済後に、100万円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>を使用し、繰上げ返済額は100万円を超えない範囲での最大額とすること。また、繰上げ返済に伴う手数料等については考慮しないものとする。
<資料:長岡家の住宅ローンの償還予定表の一部>




| 1. | 9ヵ月 |
| 2. | 1年1ヵ月 |
| 3. | 1年2ヵ月 |
| 4. | 1年3ヵ月 |
正解:3
15,107,049円-100万円=14,107,049円です。
14,107,049円より大きい額で最小の額は、134回返済後の14,159,930円ですから、短縮期間は121回~134回の14ヵ月(1年2ヵ月)となります。
【問29】
京介さんは、住宅ローンの見直しについてFPの五十嵐さんに質問をした。一般的な住宅ローンの見直しに関する五十嵐さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「より有利な条件の住宅ローンを扱う金融機関に住宅ローンの『借換え』をする場合、抵当権の抹消や設定費用、事務手数料などの諸費用が必要になります。」 |
| 2. | 「通常の返済とは別にローンの元金部分の一部を返済する『繰上げ返済』をした場合、その元金に対応する利息部分の支払いがなくなり、総返済額を減らす効果があります。」 |
| 3. | 「現在の住宅ローンの借入先の金融機関において、返済期間を延長することで月々の返済額を減額したり、一定期間、月々の返済額を利息の支払いのみにする『条件変更』ができる場合もあります。」 |
| 4. | 「固定金利選択型10年で借り入れている場合、現在の固定期間が終了した後は固定金利選択型10年で自動更新され、他の固定金利選択型や変動金利型を選択することはできません。」 |
正解:4
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | 固定金利選択型ローンの固定金利期間終了時には、固定金利または変動金利を選択することができます。 |
【問30】
下記<資料>に基づく京介さんの自宅に係る年間の地震保険料を計算しなさい。なお、京介さんの自宅は京都府にあるイ構造のマンションで、火災保険の保険金額は1,400万円で、地震保険の保険金額は、2023年9月1日現在の火災保険の保険金額に基づく契約可能な最大額であり、地震保険料の割引制度は考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料:年間保険料例(地震保険金額100万円当たり、割引適用なしの場合)>




正解:5,110(円)
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、730円です。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
【問31】
京介さんが加入している保険から保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
| (ア) | 京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 |
| (イ) | 京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。 |
| (ウ) | 自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税 (一時所得)の課税対象となる。 |
| (エ) | 自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、 非課税となる。 |
正解:○、×、×、○
| (ア) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じである生命保険の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。 |
| (イ) | リビングニーズ特約の生前給付金は、受け取った時点では非課税ですが、死亡時に使い切れていない残額は相続税の課税対象となります。 |
| (ウ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(損害保険金)は、非課税です。 |
| (エ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(地震火災費用保険金)は、非課税です。 |
【問32】
京介さんは、病気療養のため2023年8月に7日間入院した。京介さんの2023年8月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、京介さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は30万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。
<資料>




| 1. | 41,180円 |
| 2. | 80,100円 |
| 3. | 84,430円 |
| 3. | 125,570円 |
正解:4
窓口での自己負担分(総医療費の3割)が21万円ですから、総医療費は、21万円÷0.3=70万円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
【問33】
秋穂さんは、京介さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの五十嵐さんに質問をした。京介さんが2023年9月に45歳で在職中に死亡した場合、京介さんの死亡時点において秋穂さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、京介さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「京介さんが2023年9月に死亡した場合、秋穂さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。秋穂さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翔太さんを対象とする子の加算額を加えた額です。翔太さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( ア )相当額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが( ウ )に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( ア )相当額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが( ウ )に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
<語群>
1.2分の1 2.3分の2 3.4分の3
4.240月 5.300月 6.360月
7.60歳 8.65歳 9.70歳
1.2分の1 2.3分の2 3.4分の3
4.240月 5.300月 6.360月
7.60歳 8.65歳 9.70歳
正解:3、5、8
| (ア) | 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
| (イ) | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。 |
| (ウ) | 中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻などに対して、妻が65歳に達するまで支給されます。 |
【問34】
秋穂さんは、今後、正社員からパートタイマーに勤務形態を変更し、京介さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となることを検討しているため、FPの五十嵐さんに相談をした。協会けんぽの被扶養者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。
「被扶養者になるには、主として被保険者により生計を維持していることおよび原則として、日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準は、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が( ア )未満(60歳以上の人または一定の障害者は<***>未満)で、被保険者の収入の( イ )未満であることとされています。
被扶養者となる人の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。なお、雇用保険の失業給付や公的年金等は、収入に( ウ )。」
被扶養者となる人の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。なお、雇用保険の失業給付や公的年金等は、収入に( ウ )。」
<語群>
1.103万円 2.130万円 3.150万円
4.3分の1 5.2分の1 6.3分の2
7.含まれます 8.含まれません
1.103万円 2.130万円 3.150万円
4.3分の1 5.2分の1 6.3分の2
7.含まれます 8.含まれません
正解:2、5、7
| (ア) | 健康保険の被扶養者となるためには、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上の人等は180万円未満)であるなどの要件を満たす必要があります。 |
| (イ) | 健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であるなどの要件を満たす必要があります。 |
| (ウ) | 被扶養者となるか否かを判定する際、年間収入の額には、公的年金の額や、社会保険からの給付の額を含みます。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |