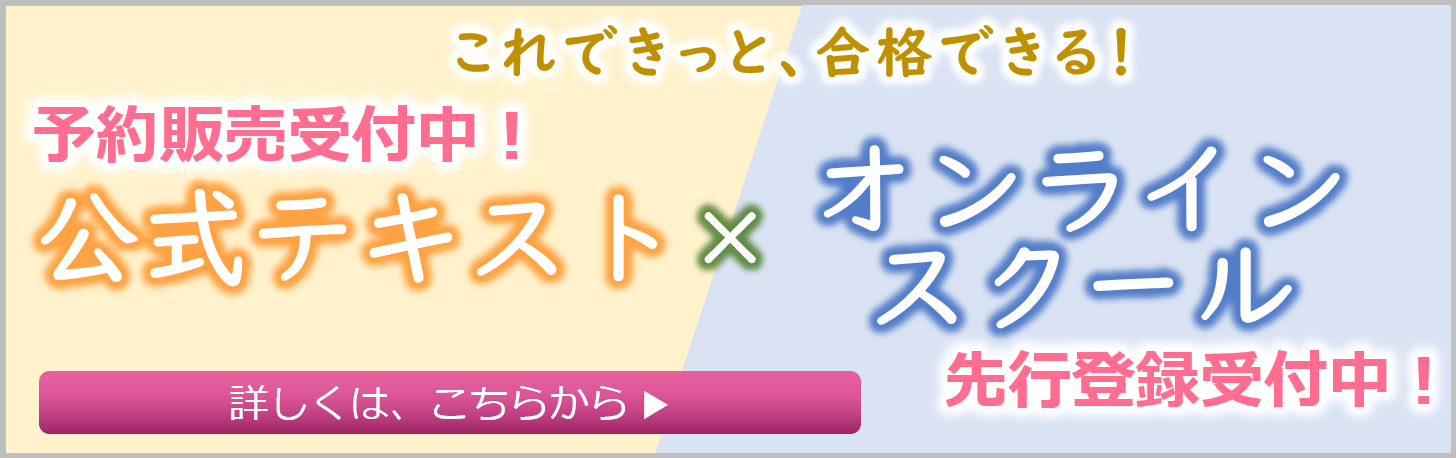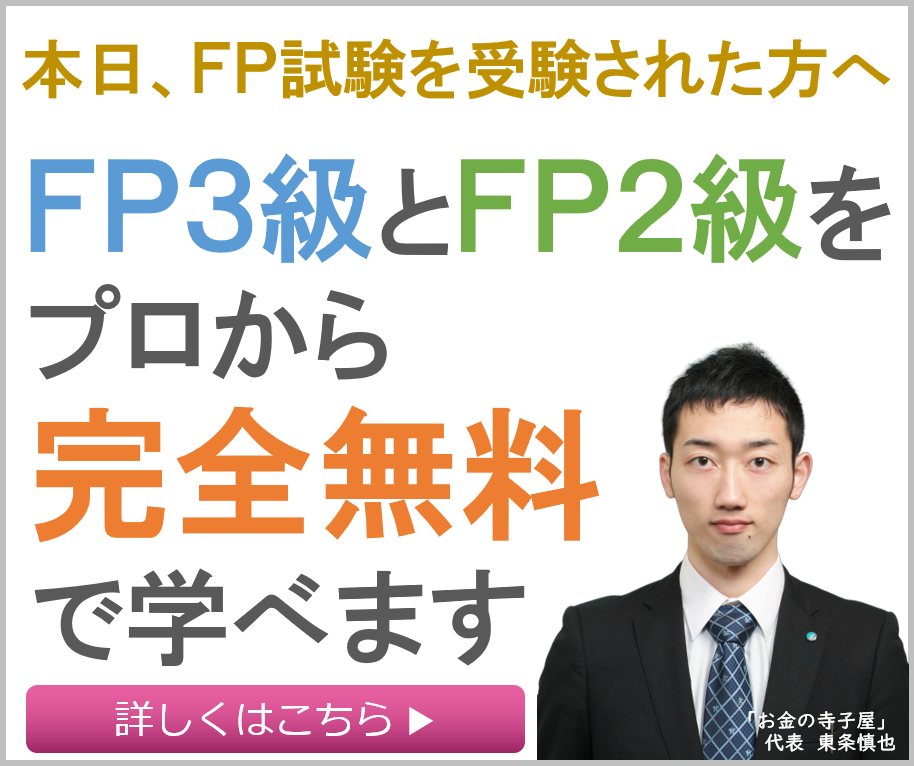FP2級学科解説-2022年5月・問31~40
【問31】
所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。 |
| 2. | 合計所得金額は、損益通算後の各種所得の金額の合計額に、純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額である。 |
| 3. | 課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額に応じて7段階に区分された税率を用いて計算される。 |
| 4. | 所得税では、納税者本人が所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 合計所得金額とは損益通算後の各種所得の金額の合計額を言い、純損失や雑損失の繰越控除を適用する前の金額です。 |
| 3. | 正しい記述です。課税総所得金額に適用される所得税率は、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過累進税率です。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問32】
次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。
| 1. | 納税者本人が特別障害者である場合 |
| 2. | 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合 |
| 3. | 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合 |
| 4. | 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合 |
| 正解:4 | |
| その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、本人が特別障害者に該当する、23歳未満の扶養親族を有する、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する、のうち、いずれかに該当する人は、所得金額調整控除の適用を受けることができます。 |
【問33】
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
| 1. | 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額 |
| 2. | 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額 |
| 3. | 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額 |
| 4. | ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額 |
| 正解:1 | |
| 1. | 不動産所得の計算上必要経費に算入された借入金の利子のうち、土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象外ですが、土地取得目的ではない借入金の利子は損益通算の対象です。 |
| 2. | 生活用動産の譲渡にかかる所得は非課税ですから、譲渡損失が生じた場合でも損益通算することはできません。 |
| 3. | 生活に通常必要でない資産の譲渡にかかる損失は、損益通算することができません。 |
| 4. | 生活に通常必要でない資産の譲渡にかかる損失は、損益通算することができません。 |
【問34】
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
| 1. | 納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。 |
| 2. | 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。 |
| 3. | 医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。 |
| 4. | 納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方の有無に関わらず、医療費控除の対象となります。 |
【問35】
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。 |
| 2. | 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。 |
| 3. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。 |
| 4. | 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 住宅ローンの対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 住宅ローンの適用を受けるためには、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き住み続ける必要があります。 |
| 4. | 給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、最初の年は必ず確定申告をしなくてはいけません(2年目以降は年末調整によって適用を受けることができます)。 |
【問36】
個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。 |
| 2. | 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。 |
| 3. | 所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。 |
| 4. | 納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 個人住民税は、その年の1月1日時点に居住している市町村に納めます。 |
| 2. | 個人住民税の所得割は、前年の所得金額を基に計算されます |
| 3. | 住民税は賦課課税方式の税金ですから、基本的に、確定申告をする必要はありません。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問37】
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。 |
| 2. | 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。 |
| 3. | 法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。 |
| 4. | 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 法人税や法人住民税は、益金を得るために必要なお金ではなく、利益の処分ですから、損金には算入されません。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問38】
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。 |
| 2. | 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。 |
| 3. | 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。 |
| 4. | 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 簡易課税制度を選択した場合、原則として、2年間は簡易課税をやめることができません。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問39】
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。 |
| 2. | 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。 |
| 3. | 会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。 |
| 4. | 会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 役員が会社に無利息で金銭の貸付を行った場合には、課税関係は生じません。 |
| 3. | 正しい記述です。法人が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その法人の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額が、益金の額に算入されます(時価と取得価格との差額が譲渡損益となり、時価と譲渡対価の差額が受贈益として益金額に算入されます)。 |
| 4. | 正しい記述です。法人税法上、法人が無償による資産の譲渡又は役務の提供を行った場合、(お金を受け取っていなくても、正当な対価を得たと考えて)益金を認識しなくてはいけません。 |
【問40】
企業の決算書および法人税の申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 貸借対照表は、決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を示したものである。 |
| 2. | 損益計算書は、企業の資金の調達源泉とその用途を示したものである。 |
| 3. | キャッシュフロー計算書は、一会計期間における企業の資金の増減を示したものである。 |
| 4. | 法人税法上の所得金額は、確定した決算に基づく企業会計上の当期純利益または当期純損失を基に申告調整を行い、計算される。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を表したものです。なお、問題文は貸借対照表の説明です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |