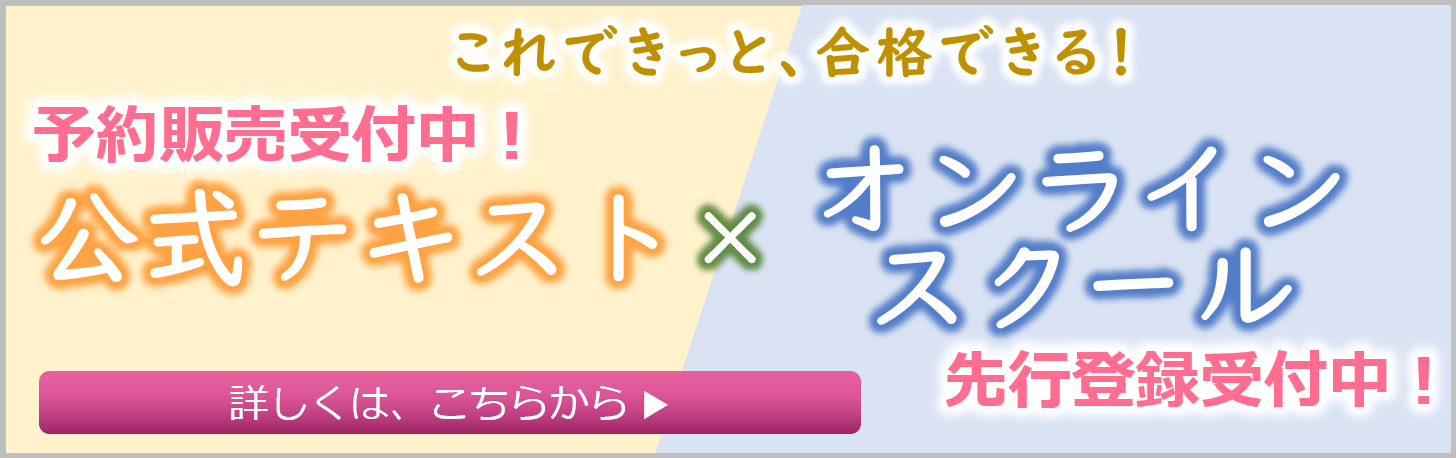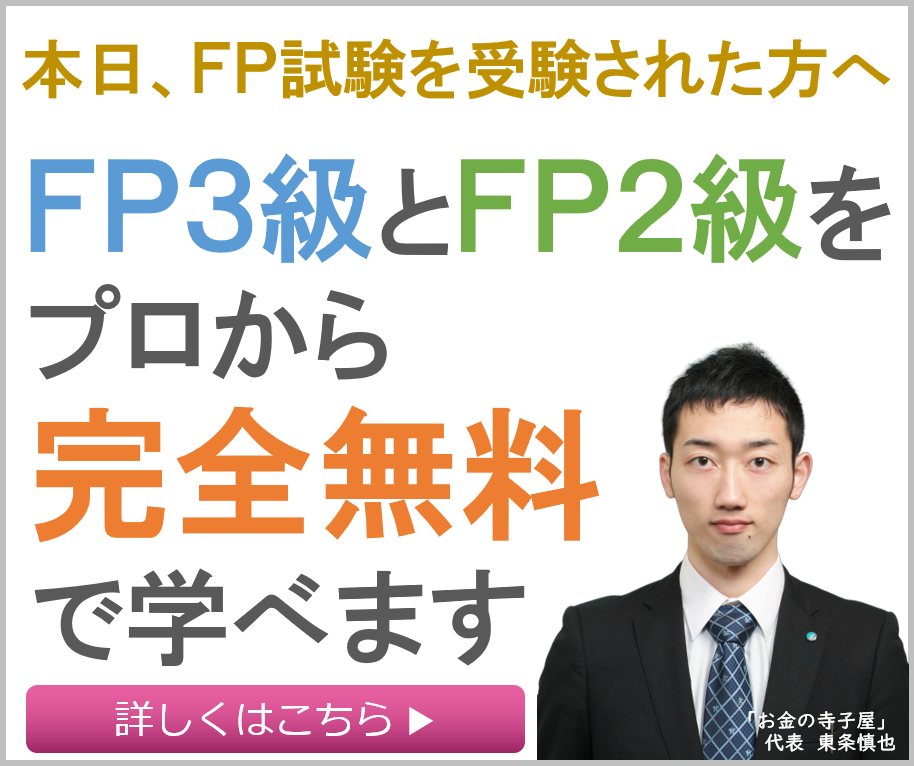FP2級学科解説-2022年5月・問1~10
【問1】
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。 |
| 2. | 生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。 |
| 3. | 税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。 |
| 4. | 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 投資一任契約に基づき、顧客の資産の運用を行うためには、金融商品取引業の登録を受けなくてはいけません。 |
| 2. | 生命保険の一般的な商品性や目的別の活用方法は、誰でも説明することができます。 |
| 3. | 税制の一般的な説明は誰でもすることができます。 |
| 4. | 法律の一般的な説明は誰でもすることができます。 |
【問2】
ライフプランの作成の際に活用される下記<資料>の各種係数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>年率2%、期間10年の各種係数
| 終価係数 | 1.2190 |
| 現価係数 | 0.8203 |
| 年金終価係数 | 10.9497 |
| 減債基金係数 | 0.0913 |
| 年金現価係数 | 8.9826 |
| 資本回収係数 | 0.1113 |
| 1. | 元本100万円を10年間にわたり、年率2%で複利運用した場合の元利合計額は、「100万円×1.2190」で求められる。 |
| 2. | 年率2%で複利運用しながら10年後に100万円を得るために必要な毎年の積立額は、「100万円×0.0913」で求められる。 |
| 3. | 10年間にわたり、年率2%で複利運用しながら、毎年100万円を受け取るために必要な元本は、「100万円×10.9497」で求められる。 |
| 4. | 年率2%で複利運用しながら10年後に100万円を得るために必要な元本は、「100万円×0.8203」で求められる。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 一括型運用における将来の金額を求める際に用いる係数は、終価係数です。 |
| 2. | 積立型運用における毎年の積立額を求める際に用いる係数は、減債基金係数です。 |
| 3. | 取り崩し型運用における必要な元本を求める際に用いる係数は、年金現価係数です。 |
| 4. | 一括型運用における現在の金額を求める際に用いる係数は、現価係数です。 |
【問3】
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定められている。 |
| 2. | 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。 |
| 3. | 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。 |
| 4. | 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 労災事故が発生する確率は業種ごとに違いがありますから、労災保険料率は事業の種類ごとに定められています。 |
| 2. | 休業補償給付は、休業4日目から支給されます。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | 障害補償年金は、障害等級1級から7級の人に支払われ、障害補償一時金は、障害等級8級から14級の人に支払われるものですから、これらはどちらかを選択して受給するものではありません。 |
【問4】
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。 |
| 2. | 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。 |
| 3. | 育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。 |
| 4. | 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。雇用保険の給付のうち失業等給付と育児休業給付は労働者が受け取るものですから、これらにかかる保険料は労使折半します。一方、雇用二事業は主に事業主に利益があるものですから、その財源に係る保険料は事業主のみが負担します。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 育児休業給付の受給資格は、原則として、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間(育児休業開始日の前日から1ヵ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヵ月以上ある事とされています。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問5】
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。 |
| 2. | 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。 |
| 3. | 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。 |
| 4. | 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 外国籍の人も、日本に住所を有していれば国民年金の被保険者となります。 |
| 2. | 公的年金を繰上げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げる必要がありますが、繰下げる場合は別々に繰下げることができます。 |
| 3. | 老齢厚生年金に加給年金が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある必要があります。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問6】
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。 |
| 2. | 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。 |
| 3. | 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。 |
| 4. | 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
| 4. | 正しい記述です。老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給されますが老齢厚生年金が優先されます。よって、遺族厚生年金の方が多い場合には、これらの差額が遺族厚生年金として支払われ、老齢厚生年金の方が多い場合には、遺族厚生年金は全額支給停止されます。 |
【問7】
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。 |
| 2. | 企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。 |
| 3. | 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で7万円である。 |
| 4. | 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。マッチング拠出をする際の加入者掛金は、事業主掛金と合わせて限度額以下、かつ、事業主掛金以下とされています。 |
| 2. | 正しい記述です。 |
| 3. | 国民年金の第1号被保険者が拠出することができる確定拠出年金の掛金の拠出限度額(月額)は、国民年金基金と合わせて68,000円までです。 |
| 4. | 正しい記述です。 |
【問8】
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。 |
| 2. | 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。 |
| 3. | 小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。 |
| 4. | 国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 中退共に加入することができる(共済契約者になることができる)企業は、業種ごとに定められた常用従業員数または資本金・出資金の要件を満たす企業です。 小売業は、常用従業員数が50人以下、または、資本金・出資金の額が5千万円以下でなければ、加入することができません。 |
| 2. | 正しい記述です。中退共の退職金は、退職時に一括して受け取る一時払い、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い(一定の要件を満たす必要あり)、これらを併用する併用払いの3つの方法があります。 |
| 3. | 小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者一人につき、7万円が上限となっています(1,000円~70,000円まで500円刻み)。 |
| 4. | 国民年金基金の給付には、老齢年金と遺族一時金の2つがあります。 |
【問9】
Aさんが、下記<資料>に基づき、住宅ローンの借換えを行った場合、借換え後10年間の返済軽減額の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、返済は年1回であるものとし、計算に当たっては下記<係数>を使用すること。また、記載のない条件については考慮しないものとする。
<資料>
[Aさんが現在返済中の住宅ローン]
借入残高:1,000万円
利 率:年%の固定金利
残存期間:10年
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
[Aさんが借換えを予定している住宅ローン]
借入金額:1,000万円
利 率:年2%の固定金利
返済期間:10年
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
| <係数>期間10年の各種係数 | |||
| 現価係数 | 減債基金係数 | 資本回収係数 | |
| 2% | 0.8203 | 0.0913 | 0.1113 |
| 3% | 0.7441 | 0.0872 | 0.1172 |
| 1. | (1,000万円×0.8203×10年)-(1,000万円×0.7441×10年) |
| 2. | (1,000万円×0.0913×10年)-(1,000万円×0.0872×10年) |
| 3. | (1,000万円×0.1113×10年)-1,000万円 |
| 4. | (1,000万円×0.1172×10年)-(1,000万円×0.1113×10年) |
| 正解:4 | |
| 借り換えた場合の返済軽減額は、「現在のローンの総返済額-借り換えたローンの総返済額」の式で計算されます。 また、元利均等返済を行う場合、総返済額は、「借入残高×借入金利と残存期間に基づく資本回収係数×残存期間」で計算されます。 |
【問10】
決算書に基づく経営分析指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 損益分岐点比率は、実際の売上高に対する損益分岐点売上高の割合を示したものであり、一般に、この数値が低い方が企業の収益性が高いと判断される。 |
| 2. | 自己資本比率は、総資本に対する自己資本の割合を示したものであり、一般に、この数値が低い方が財務の健全性が高いと判断される。 |
| 3. | 固定長期適合率は、自己資本に対する固定資産の割合を示したものであり、一般に、この数値が低い方が財務の健全性が高いと判断される。 |
| 4. | ROEは、自己資本に対する当期純利益の割合を示したものであり、一般に、この数値が低い方が経営の効率性が高いと判断される。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 正しい記述です。損益分岐点比率=損益分岐点売上高÷売上高ですから、この値が低いほど収益性が高いと判断されます。 |
| 2. | 自己資本比率=自己資本÷総資本ですから、この値が高い方が財務の健全性が高いと判断されます。 |
| 3. | 固定長期適合率=固定資産÷(固定負債+自己資本)ですから、この値が低いほど財務の健全性が高いと判断されます。 |
| 4. | ROE=当期純利益÷自己資本ですから、この数値が高いほど経営の効率性が高いと判断されます。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |