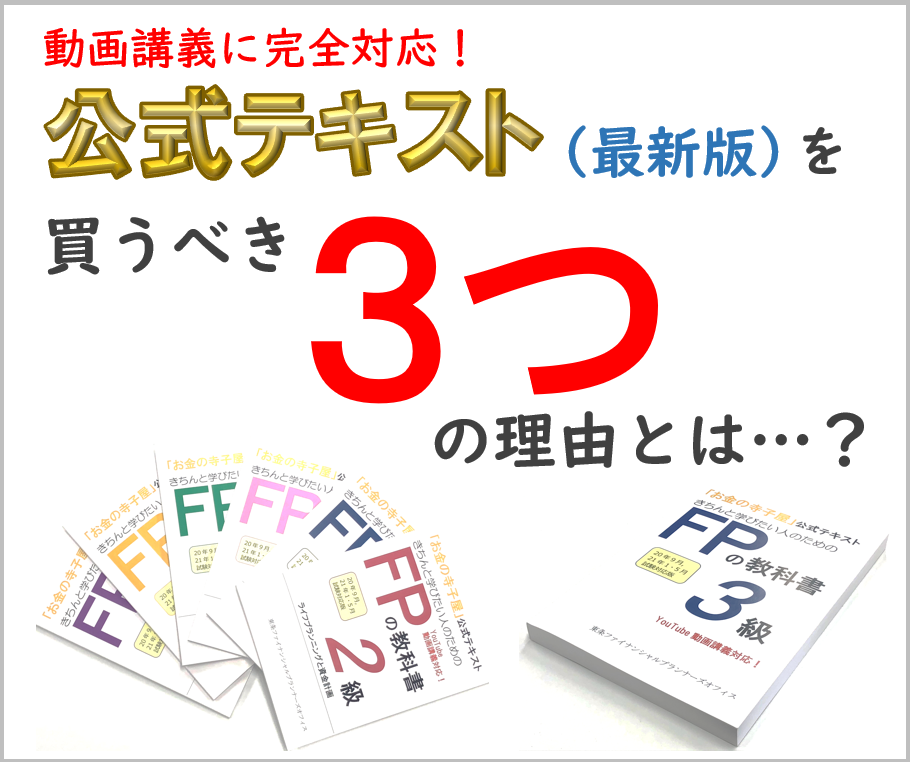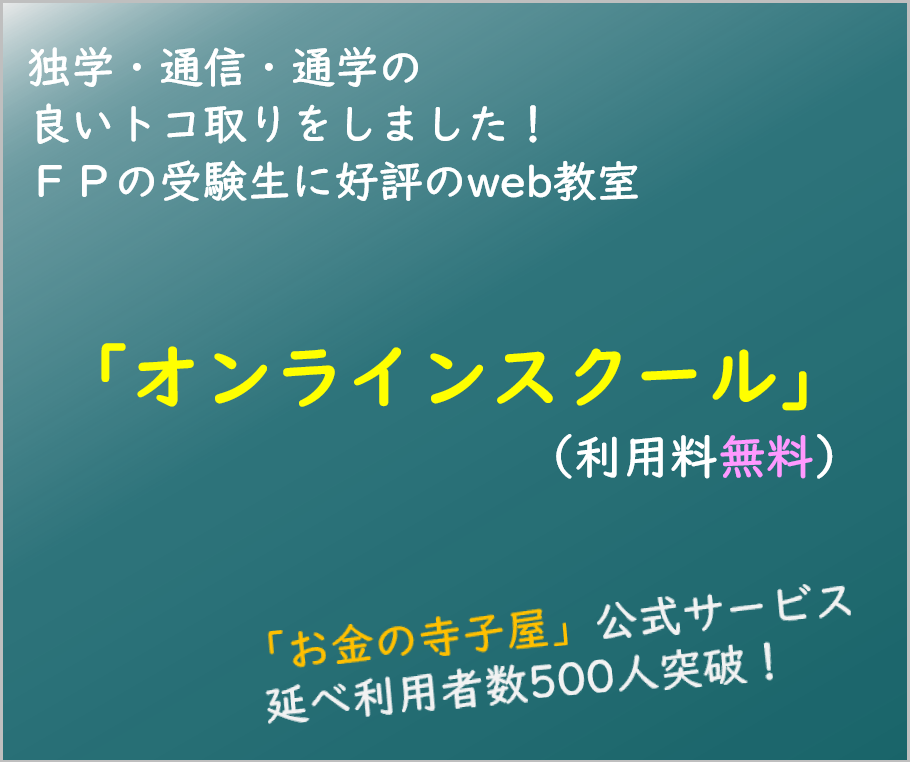正誤問題(FP2) 10種類の所得1(1/2)
2025.6~2026.5試験対応済み
【問1】★
利子所得は、預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金、友人に貸したお金に係る利子等が該当する
【答1】
×:友人に貸したお金に係る利子は雑所得です。
【問2】★
配当所得は、株式の配当、株式投資信託の収益分配金、株を売却したことによる利益等が該当する。
【答2】
×:株を売却したことによる利益は譲渡所得です。
【問3】★
総合課税を選択した上場株式の配当所得は、配当控除の対象となる。
【答3】
○:配当金の課税方法は3種類(NISAの非課税を含めると4種類)あり、配当控除を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した場合に限られます。
【問4】★
申告不要制度を選択した配当所得は、20%の所得税と住民税が源泉徴収され、課税関係が終了する。
【答4】
○:申告不要制度を選択した配当所得は、20%の所得税と住民税が源泉徴収され、収入が無かったものとみなされます(扶養の判定上有利になりますが、配当控除や損益通算等のメリットはありません)。
【問5】★
申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は、配当控除の対象となる。
【答5】
×:配当控除を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した配当所得に限られます。
【問6】★
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる。
【答6】
×:申告分離課税を選択した配当所得のみ、株式等に係る譲渡所得との損益通算の対象となります。
【問7】★
申告不要を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる。
【答7】
×:株式等に係る譲渡所得との損益通算の対象となるのは、申告分離課税を選択した配当所得に限られます。
【問8】★
申告分離課税を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができるが、配当控除の適用を受ける事はできない。
【答8】
○:株式等に係る譲渡損失と損益通算は、申告分離課税を選択した配当所得だけのメリットであり、配当控除は、総合課税を選択した配当所得だけのメリットです。
【問9】★
所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得となる。
【答9】
×:不動産の貸し付けによる所得は、規模を問わず不動産所得となります。
【問10】★
不動産所得の計算上、借入金の元金返済額と利子の支払額は、必要経費に算入される。
【答10】
×:借入金の元金返済額は、必要経費に算入されません。
【問11】
不動産所得の計算において、敷金は、返還を要しないことが確定した時点で収入金額に計上される。
【答11】
○:不動産所得の計算において、賃借人に返還しないものはすべて収入金額に含まれると考えてください。但し、敷金を収入に計上しても、同額が修繕費として費用に計上されるため、所得(=税額)は増えません。
【問12】★
青色申告者は、不動産所得の計算上、電子申告要件等を満たさない場合、青色申告特別控除として10万円または55万円を控除する事が出来る。
【答12】
○:青色申告特別控除は記帳の手間賃のようなイメージです。事業的規模なら帳簿をつけるのが大変なので55万円、事業的規模でないなら帳簿をつける手間はさほどかからないので10万円という事です。なお、電子申告要件等を満たした場合、55万円の上限は65万円になります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |