FP3級実技(個人)解説-2023年9月・後半
【問10】~【問12】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(55歳)は、昨年、父親の相続によりX市内の実家(甲土地および建物)を取得した。法定相続人は、長男のAさんのみであり、相続に係る申告・納税等の手続は完了している。
Aさんは、別の都市に自宅を所有し、家族と居住しているため、相続後に空き家となっている実家(築45年)の売却を検討している。しかし、先日、友人の不動産会社の社長から、「甲土地は、最寄駅から徒歩5分の好立地にあり、相応の住宅需要が見込める。自己建設方式による賃貸マンションの建築を検討してみてはどうか」との提案があったことで、甲土地の有効活用にも興味を持ち始めている。
Aさん(55歳)は、昨年、父親の相続によりX市内の実家(甲土地および建物)を取得した。法定相続人は、長男のAさんのみであり、相続に係る申告・納税等の手続は完了している。
Aさんは、別の都市に自宅を所有し、家族と居住しているため、相続後に空き家となっている実家(築45年)の売却を検討している。しかし、先日、友人の不動産会社の社長から、「甲土地は、最寄駅から徒歩5分の好立地にあり、相応の住宅需要が見込める。自己建設方式による賃貸マンションの建築を検討してみてはどうか」との提案があったことで、甲土地の有効活用にも興味を持ち始めている。
<甲土地の概要>




| ・ | 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
| ・ | 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問10】
甲土地に耐火建築物を建築する場合の①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | ①360㎡ ②1,440㎡ |
| 2. | ①360㎡ ②1,600㎡ |
| 3. | ①400㎡ ②1,600㎡ |
正解:1(4点)
| ① | 準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、80%+10%=90%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、400㎡×90%=360㎡です。 |
| ② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、360%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、400㎡×360%=1,440㎡です。 |
【問11】
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があります」 |
| 2. | 「本特例の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければなりません」 |
| 3. | 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」 |
正解:2(3点)
| 1) | 正しい記述です。本特例は、質の低い家が空き家として放置されることを防ぐ目的で、取り壊しやリノベーションを促す制度ですから、旧耐震基準で建てられた住宅を対象としています(新耐震基準は、1981年6月1日以降の建築確認から適用されている)。 |
| 2) | 相続空き家の特例の適用を受けるためには、譲渡対価の額が1億円以下である等の要件を満たす必要があります。 |
| 3) | 正しい記述です。 |
【問12】
甲土地の有効活用等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 「自己建設方式とは、Aさんが所有する土地の上に、事業者が建設資金を負担してマンション等を建設し、完成した建物の住戸等をAさんと事業者がそれぞれの出資割合に応じて取得する手法です」 |
| 2. | 「甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、相続税の課税価格の計算上、330㎡までの部分について50%の減額が受けられます」 |
| 3. | 「Aさんが金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建築した場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、当該借入金の残高は債務控除の対象となります」 |
正解:3(3点)
| 1) | 自己建設方式は、自身が所有する土地の上に自己資金で賃貸用建物を建て、自身で賃貸業務を営む手法です。問題文は、等価交換方式の説明です。 |
| 2) | 貸付事業用宅地等は、相続税の課税価格の計算上、200㎡までの部分について50%の減額が受けられます。 |
| 3) | 正しい記述です。被相続人の債務のうち、返済することが確実であるものは、債務控除の対象です。 |
【問13】~【問15】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(83歳)は、妻Bさん(81歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には2人の子がいるが、Aさんは、孫Eさん(24歳)にも相応の資産を承継させたいと考えており、遺言の作成を検討している。
Aさん(83歳)は、妻Bさん(81歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には2人の子がいるが、Aさんは、孫Eさん(24歳)にも相応の資産を承継させたいと考えており、遺言の作成を検討している。
<Aさんの親族関係図>




| <Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)> | ||
| 現預金 | : | 3,000万円 |
| 上場株式 | : | 4,000万円 |
| 自宅(土地250㎡) | : | 5,000万円(注) |
| 自宅(建物) | : | 1,000万円 |
| 賃貸マンション(土地400㎡) | : | 1億円(注) |
| 賃貸マンション(建物) | : | 8,000万円 |
| 合計 | : | 3億1,000万円 |
| (注) | 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問13】
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」 |
| 2. | 「自筆証書遺言は、所定の手続により法務局(遺言書保管所)に保管することができますが、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認手続が必要となります」 |
| 3. | 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」 |
正解:1(3点)
| 1) | 正しい記述です。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要で、遺言者が口述した内容を公証人が遺言の形式に落とし込みます。 |
| 2) | 自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局に保管された自筆証書遺言は、改ざんなどの恐れが無いため、検認手続きが不要です。 |
| 3) | 遺留分が侵害された遺言は、それを理由として直ちに無効になる訳ではありません。 |
【問14】
仮に、Aさんの相続が現時点(2023年9月10日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億1,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
| <資料>相続税の速算表(一部抜粋) | ||
| 法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 |
30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 |
40% | 1,700万円 |
| 20,000万円超 30,000万円以下 |
45% | 2,700万円 |
| 1. | 3,500万円 |
| 2. | 4,250万円 |
| 3. | 6,750万円 |
正解:2(4点)
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億1,000万円×1/2=1億500万円となります。
これに対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、2億1,000万円×1/4=5,250万円となります。
これに対応する相続税額は、5,250万円×30%-700万円=875万円です。
したがって、相続税の総額は、2,500万円+875万円+875万円=4,250万円となります。
これに対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、2億1,000万円×1/4=5,250万円となります。
これに対応する相続税額は、5,250万円×30%-700万円=875万円です。
したがって、相続税の総額は、2,500万円+875万円+875万円=4,250万円となります。
【問15】
現時点(2023年9月10日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,500万円となります」 |
| 2. | 「自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません」 |
| 3. | 「孫Eさんが遺贈により財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります」 |
正解:1(3点)
| 1) | 相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
| 2) | 正しい記述です。貸付事業用宅地等と他の区分の宅地について特例の適用を受けようとする場合、所定の算式により調整計算されます。 |
| 3) | 孫が遺贈により財産を取得した場合、その孫が代襲相続人でない限り、相続税額の2割加算の対象となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |
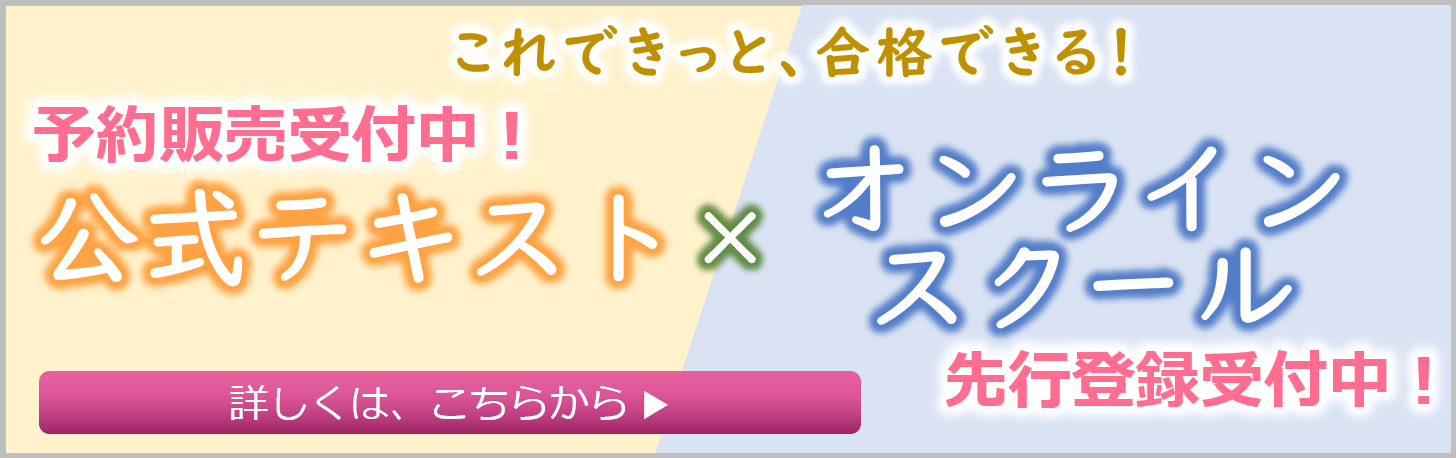

square.png)