FP3級実技(個人)解説-2022年5月・後半
【問10】~【問12】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(50歳)は、1年前に父親の相続により甲土地(500㎡)を取得している。甲土地は父親の存命中から月極駐車場として賃貸しているが、その収益性は低く、Aさんは、甲土地を有効活用できないか考えている。
そのような折、知人の不動産会社の社長から「大手ドラッグストアのX社が、新規出店にあたり、最寄駅から徒歩5分にある甲土地に興味を示している。X社は建設協力金方式を希望しているが、契約形態は事業用定期借地権方式でもよいと言っている。一方、駅周辺では再開発が進んでおり、居住用建物について相応の需要が見込まれるため、甲土地で賃貸マンション経営をしてもよいのではないか」とアドバイスを受けた。
Aさん(50歳)は、1年前に父親の相続により甲土地(500㎡)を取得している。甲土地は父親の存命中から月極駐車場として賃貸しているが、その収益性は低く、Aさんは、甲土地を有効活用できないか考えている。
そのような折、知人の不動産会社の社長から「大手ドラッグストアのX社が、新規出店にあたり、最寄駅から徒歩5分にある甲土地に興味を示している。X社は建設協力金方式を希望しているが、契約形態は事業用定期借地権方式でもよいと言っている。一方、駅周辺では再開発が進んでおり、居住用建物について相応の需要が見込まれるため、甲土地で賃貸マンション経営をしてもよいのではないか」とアドバイスを受けた。
<甲土地の概要>


| ・ | 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
| ・ | 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問10】
甲土地に耐火建築物を建築する場合の①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | ① 300㎡ ② 1,500㎡ |
| 2. | ① 350㎡ ② 1,500㎡ |
| 3. | ① 350㎡ ② 1,600㎡ |
正解:2(4点)
| ① | 防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されますから、甲土地の建蔽率の上限は、60%+10%=70%となります。 よって、建蔽率の上限となる建築面積は、500㎡×70%=350㎡となります。 |
| ② | 前面道路の幅員によって定まる容積率の上限は、8m×4/10=3.2(320%)です。 前面道路の幅員が12m未満である場合、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率 のうち、どちらか小さい方を適用しますから甲土地の容積率の上限は、300%となります。 よって、容積率の上限となる延べ床面積は、500㎡×300%=1,500㎡となります。 |
【問11】
甲土地の有効活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 「建設協力金方式は、AさんがX社から建設資金を借り受けて、X社の要望に沿った店舗を建設し、その建物をX社に賃貸する方式です。契約期間満了後は、借主であるX社が建物を撤去し、甲土地は更地で返還されます」 |
| 2. | 「事業用定期借地権方式は、X社が甲土地を一定期間賃借し、X社が甲土地上に店舗を建設する方式です。甲土地を手放すことなく、安定した地代収入を得ることができます」 |
| 3. | 「自己建設方式は、Aさんがマンション等の建設資金の調達や建設工事の発注、建物の管理・運営を自ら行う方式です。Aさん自らが貸主となって所有するマンションの賃貸を行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得する必要があります」 |
正解:2(3点)
| 1. | 建設協力金方式において、賃貸の契約期間が満了したときには、建物付きの土地が地主に返還されます。 |
| 2. | 正しい記述です。事業用定期借地権方式は、事業用定期借地権を設定して土地を賃貸し、借地人がその土地の上に建物を建て賃料を支払う方式です。 |
| 3. | 自らが所有する建物を賃貸する場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。 |
【問12】
甲土地の有効活用に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
| ⅰ) | 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は( ① )として評価されます。また、甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について( ② )の減額が受けられます」 |
| ⅱ) | 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の( ③ )の額とする特例の適用を受けることができます」 |
| 1. | ① 貸家建付地 ② 50% ③ 6分の1 |
| 2. | ① 貸家建付地 ② 80% ③ 3分の1 |
| 3. | ① 貸宅地 ② 50% ③ 3分の1 |
正解:1(3点)
| ① | 土地とその上に建っている貸家の所有者が同じである場合、その所有者が死亡した場合には、当該土地は貸家建付地として評価されます。 なお、貸宅地とは、建物を建てて使用することを目的として他人に貸している土地(借地人名義の建物が建っている土地、いわゆる底地)の事を言います。 |
| ② | 貸付事業用宅地等に該当する土地については、200㎡まで50%評価減されます。 |
| ③ | 固定資産税の計算上、居住用の建物が建っている土地については、住宅一戸につき200㎡までの部分について、課税標準が6分の1になります。 |
【問13】~【問15】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(82歳)は、妻Bさん(78歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には、2人の子がいるが、二男Dさんは既に他界している。Aさんは、孫Eさん(24歳)および孫Fさん(22歳)に対して、相応の資産を承継させたいと考えており、遺言の準備を検討している。
Aさん(82歳)は、妻Bさん(78歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には、2人の子がいるが、二男Dさんは既に他界している。Aさんは、孫Eさん(24歳)および孫Fさん(22歳)に対して、相応の資産を承継させたいと考えており、遺言の準備を検討している。
<Aさんの親族関係図>


<Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)>
| 現預金 | : | 1億円 |
| 上場株式 | : | 4,000万円 |
| 自宅(敷地250㎡) | : | 6,000万円(注) |
| 自宅(建物) | : | 1,000万円 |
| (注) | 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問13】
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」 |
| 2. | 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となります」 |
| 3. | 「公正証書遺言は、証人3人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません」 |
正解:3(3点)
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 正しい記述です。検認は、遺言の改ざんを防止する手続きですから、改ざんの恐れが無い公正証書遺言や遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要とされています。 |
| 3. | 公正証書遺言を作成するために必要な証人の数は、2人以上です。 |
【問14】
現時点(2022年5月22日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,200万円とすることができます」 |
| 2. | 「孫Fさんが相続により財産を取得した場合、孫Fさんは相続税額の2割加算の対象となります」 |
| 3. | 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」 |
正解:2(3点)
| 1. | 正しい記述です。自宅の敷地について小規模宅地の評価減の特例を受けると、特定居住用宅地等として、330㎡まで80%評価減(相続税評価額の20%相当額が相続税の課税価格に算入)されます。 |
| 2. | 代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象外です。 |
| 3. | 正しい記述です。 |
【問15】
Aさんの相続が現時点(2022年5月22日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
| <資料>相続税の速算表 | ||
| 法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 |
30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 |
40% | 1,700万円 |
| 1. | 1,900万円 |
| 2. | 2,200万円 |
| 3. | 3,100万円 |
正解:1(4点)
各相続人の法定相続分は、妻Bさんが1/2、長男Cさんと孫Fさんがそれぞれ1/4です。
よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億2,000万円×1/2=6,000万円、長男Cさんと孫Fさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ1億2,000万円×1/4=3,000万円となります。
したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、6,000万×30%-700万円=1,100万円となり、長男Cさんと孫Fさんの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ3,000万円×15%-50万円=400万円となります。
ゆえに、相続税の総額は、1,100万円+400万円+400万円=1,900万円となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |
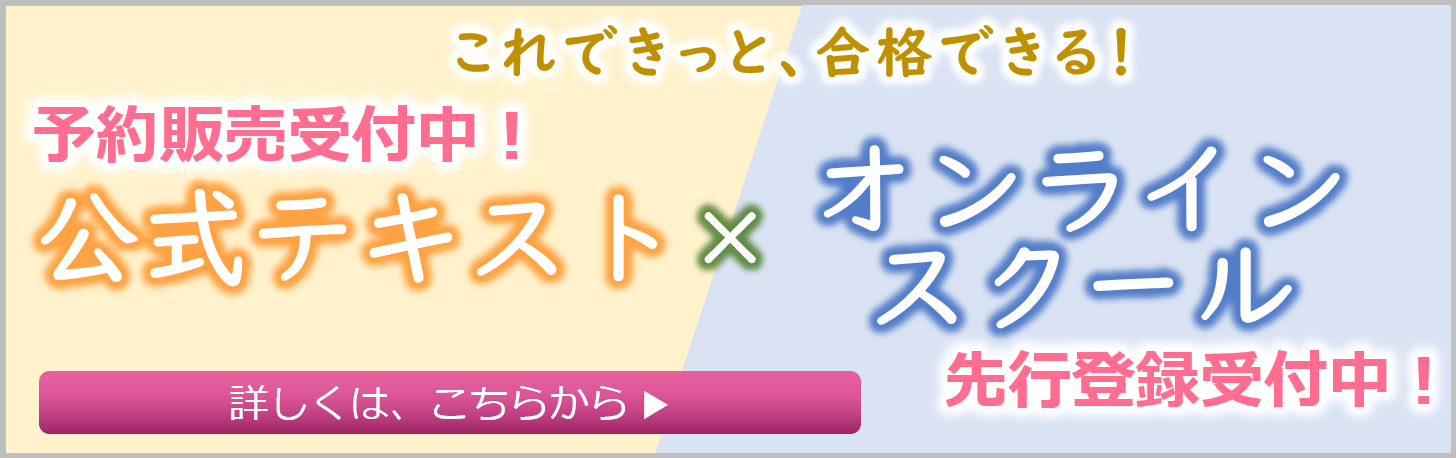

square.png)