FP3級実技(保険)解説-2023年9月・前半
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(57歳)は、妻Bさん(58歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX株式会社に勤務しており、60歳の定年後も継続雇用制度を利用して、65歳まで勤務する予定である。Aさんは、老後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。


会社員のAさん(57歳)は、妻Bさん(58歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX株式会社に勤務しており、60歳の定年後も継続雇用制度を利用して、65歳まで勤務する予定である。Aさんは、老後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
| [Aさん(1966年1月10日生まれ・会社員)] | |||
| ・ | 公的年金加入歴 | : | 下図のとおり(65歳までの見込みを含む) 20歳から大学生であった期間(27月)は国民年金に任意加入していない。 |
| ・ | 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している | ||


[妻Bさん(1965年8月17日生まれ・パートタイマー)]
| ・ | 公的年金加入歴 | : | 18歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。 |
| ・ | 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 | ||
| ※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
| ※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2023年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | 795,000円×453月/480月 |
| 2. | 795,000円×480月/480月 |
| 3. | 795,000円×513月/480月 |
正解:1(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
よって、年金額の計算に反映されるのは、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、513月-60月=453月です。
したがって、老齢基礎年金の額は、「795,000円×453/480」の算式で計算されます。
よって、年金額の計算に反映されるのは、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、513月-60月=453月です。
したがって、老齢基礎年金の額は、「795,000円×453/480」の算式で計算されます。
【問2】
次に、Mさんは、老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、繰上げ支給を請求した場合は、( ① )減額された年金が支給されることになります。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の年金の減額率は、( ② )となります。
一方、Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます。繰下げ支給の申出をした場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。Aさんの場合、繰下げの上限年齢は( ③ )です」
一方、Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます。繰下げ支給の申出をした場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。Aさんの場合、繰下げの上限年齢は( ③ )です」
| 1. | ①生涯 ②24% ③75歳 |
| 2. | ①80歳まで ②30% ③75歳 |
| 3. | ①生涯 ②30% ③70歳 |
正解:1(4点)
| ① | 公的年金の繰り上げが繰り下げの効果は一生涯続きます。 |
| ② | 老齢年金を繰上げると、1月あたり0.4%減額されますから、60歳0ヵ月から受給を開始して60月繰上げると、減額率は、0.4%/月×60月=24%となります。 |
| ③ | 1952(昭和27)年4月2日以前生まれの人、または、2017(平成29)年4月1日以降に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している人は、老齢年金を最大10年間繰下げることができます。 |
【問3】
最後に、Mさんは、公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」 |
| 2. | 「Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をしなければなりません」 |
| 3. | 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」 |
正解:2(3点)
| 1) | 特別支給の老齢厚生年金を受給するための生年月日の要件は、男性の場合、1961(昭和36)年4月1日以前生まれであること、女性の場合、1966(昭和41)年4月1日以前生まれであることです。 |
| 2) | 公的年金を繰り上げる場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはいけません。なお、 繰り下げる場合は別々に繰り下げることができます。 |
| 3) | 配偶者が年上である場合、 老齢厚生年金に加給年金が加算されることはありません。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(30歳)は、専業主婦の妻Bさん(28歳)および長女Cさん(0歳)の3人で賃貸マンションに暮らしている。Aさんは、長女Cさんの誕生を機に、生命保険の加入を検討していたところ、先日、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(30歳)は、専業主婦の妻Bさん(28歳)および長女Cさん(0歳)の3人で賃貸マンションに暮らしている。Aさんは、長女Cさんの誕生を機に、生命保険の加入を検討していたところ、先日、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:13,900円
保険料払込期間(更新限度):90歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん


保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:13,900円
保険料払込期間(更新限度):90歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん


| (注1) | 複数の特約を組み合わせて加入することができる保険 |
| (注2) | がん(悪性新生物)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態に該当した場合に一時金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
はじめに、Mさんは、現時点の必要保障額を試算することにした。下記の<算式>および<条件>に基づき、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は、次のうちどれか。
<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
| 1. | 長女Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 |
| 2. | Aさんの死亡後から長女Cさんが独立するまで(22年間)の生活費は、現在の生活費(月額25万円)の70%とし、長女Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費は、現在の生活費(月額25万円)の50%とする。 |
| 3. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金の総額は、500万円とする。 |
| 4. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金の総額は、500万円とする。 |
| 5. | 長女Cさんの教育資金および結婚援助資金の総額は、1,500万円とする。 |
| 6. | Aさん死亡後の住居費(家賃)の総額は、5,400万円とする。 |
| 7. | 死亡退職金とその他金融資産の総額は、2,000万円とする。 |
| 8. | Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、8,500万円とする。 |
| 1. | 1,970万円 |
| 2. | 3,520万円 |
| 3. | 7,370万円 |
正解:3(4点)
<遺族に必要な生活資金等>
25万円/月×70%×12ヵ月×22年=4,620万円
25万円/月×50%×12ヵ月×39年=5,850万円
死亡整理資金など:500万円
教育資金など:1,500万円
住居費:5,400万円
の、計17,870万円
25万円/月×70%×12ヵ月×22年=4,620万円
25万円/月×50%×12ヵ月×39年=5,850万円
死亡整理資金など:500万円
教育資金など:1,500万円
住居費:5,400万円
の、計17,870万円
<遺族の収入見込額>
死亡退職金と金融資産:2,000万円
公的年金等:8,500万円
の、計10,500万円
よって、必要保証額=17,870万円-10,500万円=7,370万円となります。
【問5】
次に、Mさんは、必要保障額の考え方について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | 「Aさんが将来、住宅ローン(団体信用生命保険に加入)を利用して自宅を購入した場合、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要があります」 |
| 2. | 「必要保障額を計算するうえで、公的年金の遺族給付について理解する必要があります。仮に、現時点でAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されますが、それらの給付はいずれも長女Cさんが18歳に到達した年度の3月末までとなります」 |
| 3. | 「必要保障額の算出は、Aさんが死亡したときに遺族に必要な生活資金等が不足する事態を回避するための判断材料となります。第2子の誕生など、節目となるライフイベントが発生するタイミングで、必要保障額を再計算することが大切です」 |
正解:3(3点)
| 1) | 団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んだ場合、債務者の死亡時に残債務は0となるため、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要はありません。 |
| 2) | 遺族基礎年金は、子のある配偶者または子に対して支給され、年金法上の子とは、 原則として、18歳到達年度の末日を経過していない子供を指しますから、末子である長女Cさんがしぼうすると支給停止されます。 一方、遺族厚生年金は、子がいることが要件とはされていませんから、原則として、一生涯支給されます。 |
| 3) | 適切な記述です。 |
【問6】
最後に、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
| 1. | 「必要保障額は、通常、子どもの成長とともに逓減していきますので、期間の経過に応じて年金受取総額が逓減する収入保障保険で死亡保障を準備することも検討事項の1つとなります」 |
| 2. | 「生命保険を契約する際には、傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知してください。生命保険募集人は告知受領権を有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知されることをお勧めします」 |
| 3. | 「Aさんが病気やケガで就業不能状態となった場合、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を上回る可能性があります。死亡保障だけでなく、就業不能保障の準備についてもご検討ください」 |
正解:2(3点)
| 1) | 適切な記述です。一般的に、必要保障額は、末子誕生時に最大となり、子どもの成長とともに逓減していきます。 |
| 2) | 生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権を持っているのは、一般的に、生命保険会社と生命保険会社が指定した医師だけですから、募集人や代理店に口頭で告知をしたとしても、告知を行った事にはなりません。 |
| 3) | 適切な記述です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(65歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは今期限りで勇退する予定であり、X社が加入している生命保険の解約返戻金を退職金の原資として活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(65歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは今期限りで勇退する予定であり、X社が加入している生命保険の解約返戻金を退職金の原資として活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<資料>X社が加入している生命保険に関する資料
保険の種類:長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2003年12月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
死亡・高度障害保険金額:1億円
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
年払保険料:260万円
現時点の解約返戻金額:4,200万円
現時点の払込保険料累計額:5,200万円
保険の種類:長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2003年12月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
死亡・高度障害保険金額:1億円
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
年払保険料:260万円
現時点の解約返戻金額:4,200万円
現時点の払込保険料累計額:5,200万円
| ※ | 保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を30年とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
| 1. | 1,750万円 |
| 2. | 3,500万円 |
| 3. | 3,800万円 |
正解:1(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
【問8】
Mさんは、《設例》の長期平準定期保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. | 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、保険期間の途中でピーク時期を迎え、その後は低下しますが、保険期間満了時に満期保険金が支払われます」 |
| 2. | 「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、契約は継続するため、経理処理は必要ありません」 |
| 3. | 「当該生命保険を払済終身保険に変更し、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、当該払済終身保険を役員退職金の一部としてAさんに現物支給することができます」 |
正解:3(3点)
| 1) | 長期平準定期保険は、定期保険の一種であるため、満期保険金はありません。 |
| 2) | 法人が契約している保険を払済保険にする場合、原則として、現在の資産計上額を変更時における解約返戻金の額に修正する(洗い替える)経理処理が必要です。 具体的には、現在の資産計上額を取り崩し、新しい保険の解約返戻金相当額を資産計上し、差額を雑収入または雑損失として処理します。 |
| 3) | 正しい記述です。解約返戻金のある生命保険を役員の退職時に役員に名義変更することで、退職金を支払ったものとして扱われます。 |
【問9】
X社が現在加入している《設例》の長期平準定期保険を下記<条件>にて解約した場合の経理処理(仕訳)として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 1. |   |
| 2. |   |
| 3. |   |
正解:2(4点)
<設例>の長期平準定期保険は、2019年7月7日以前に契約したものであり、保険料の払込時にその2分の1相当額を資産計上しています。
現時点の払込保険料累計額は5,200万円であることから、現時点の資産計上額は5,200万円÷2=2,600万円であると推定されます。
よって、資産計上額2,600万円を取り崩し、現金(解約返戻金)4,200万円を資産計上し、差額の1,600万円を雑収入として処理します。
現時点の払込保険料累計額は5,200万円であることから、現時点の資産計上額は5,200万円÷2=2,600万円であると推定されます。
よって、資産計上額2,600万円を取り崩し、現金(解約返戻金)4,200万円を資産計上し、差額の1,600万円を雑収入として処理します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |


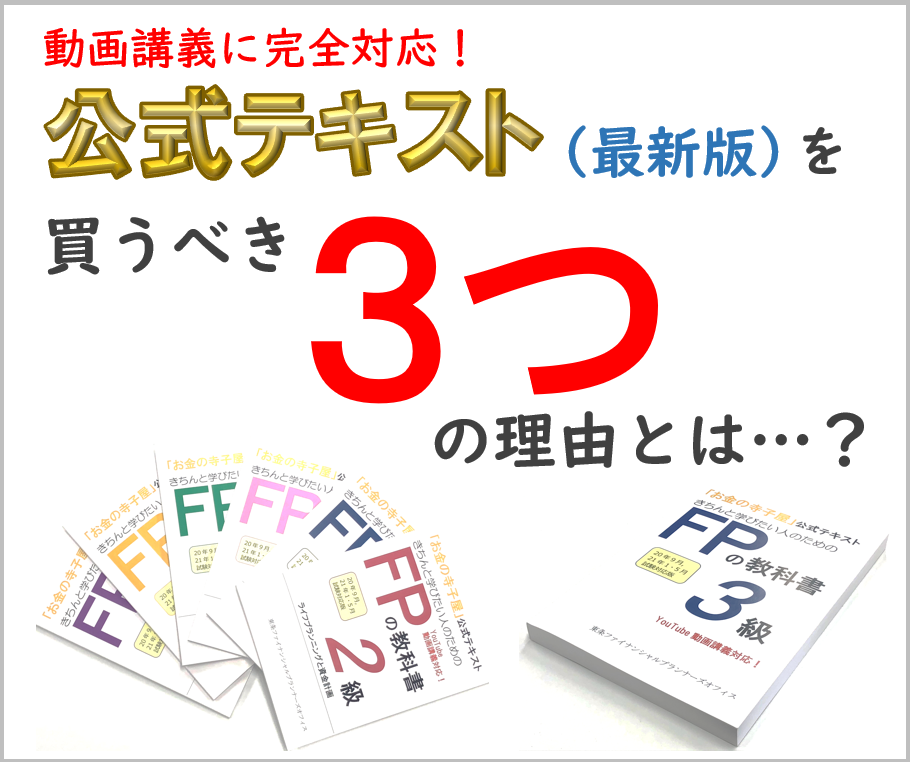
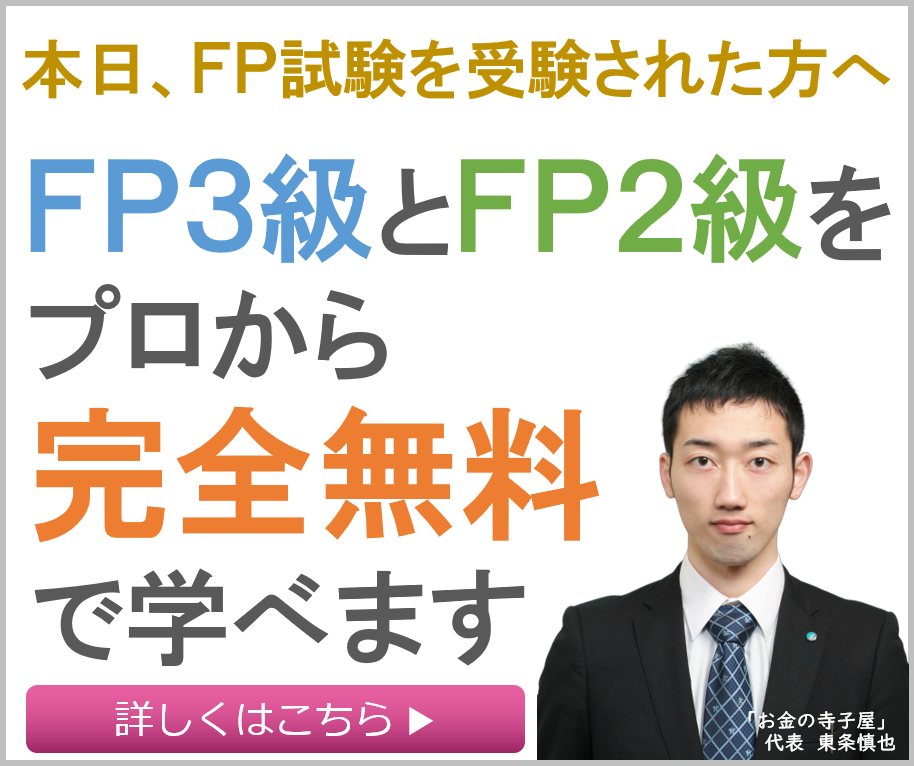
square.png)