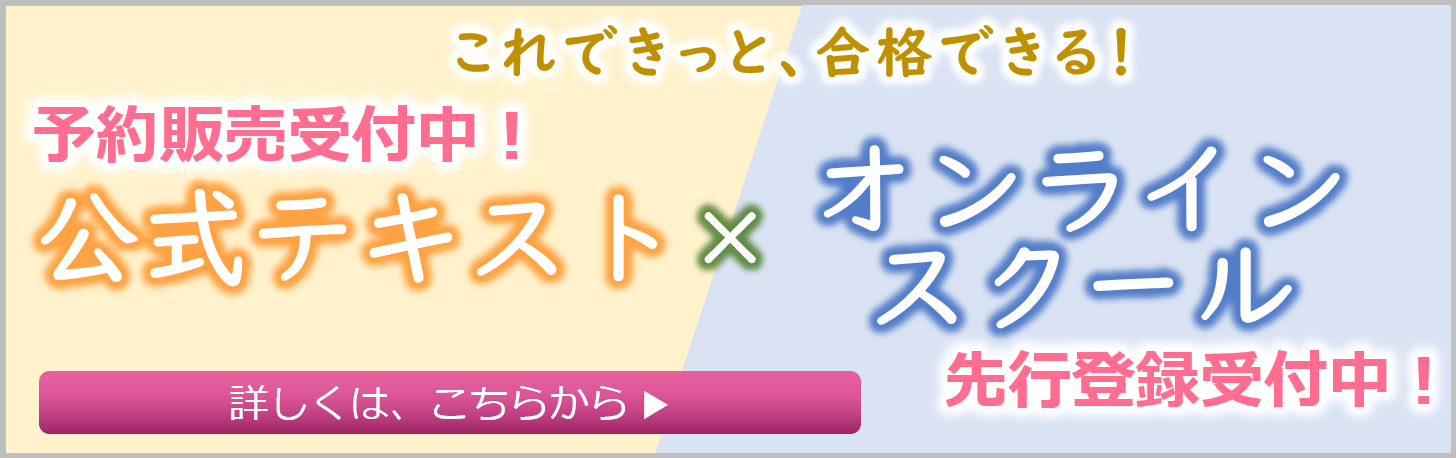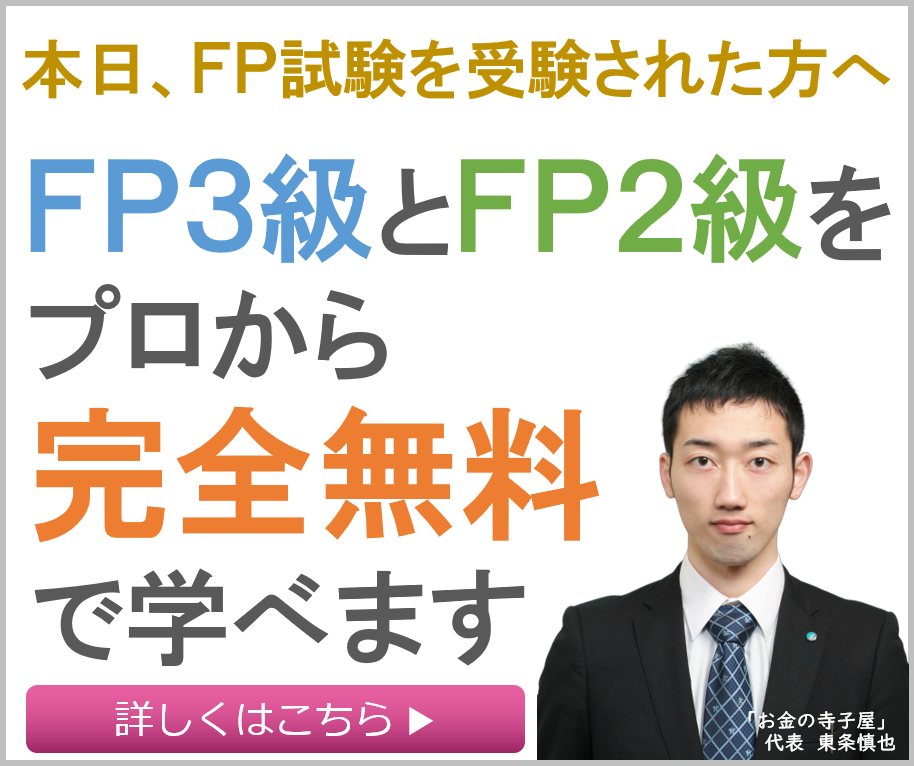FP2級実技(個人)解説-2025年1月・問1~9
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算の手順>
| 1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) | |
| ( ① )円 | |
| 2.老齢厚生年金の年金額 | |
| (1) | 報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( ② )円 |
| (2) | 経過的加算額(円未満四捨五入) ( ③ )円 |
| (3) | 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額) □□□円 |
| (4) | 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること) |
| (5) | 老齢厚生年金の年金額 ( ④ )円 |
<資料>




正解:763,300(円)、338,561(円)、213(円)、338,774(円)
| ① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、学生納付特例の適用を受けて追納をは年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(213+236)/480=763,300円となります。 |
| ② | 290,000円×5.481/1,000×213=338,561.37円≒338,561円です。 |
| ③ | 1,701円×213+816,000円×(213+236)/480=213円となります。 |
| ④ | 厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)未満ですから、加給年金は支給されません。 よって、老齢厚生年金の年金額は、338,561円+213円=338,774円となります。 |
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが75歳で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は48%となります」 |
| ② | 「Aさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額24,000円が上乗せされます」 |
| ③ | 「Aさんは、老後の年金収入を増やす方法として、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。Aさんが拠出することができる掛金の限度額は、年額276,000円です」 |
正解:×、○、×
| ① | 老齢年金を繰下げると、1月あたり0.7%増額されますから、75歳ヵ月から受給を開始して120月繰下げると、増額率は、0.7%/月×120月=84%となります。 |
| ② | 正しい記述です。付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、120月付加保険料を納付すると、付加年金の額は、200円×120=24,000円となります。 |
| ③ | <設例>より、Aさんは個人事業主(=国民年金の第1号被保険者)ですから、確定拠出年金の掛金の拠出限度額は、816,000円です。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
| Ⅰ | 「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある( ① )年金A型と保証期間のない( ① )年金B型のいずれかを選択します。2口目以降は、2種類の( ① )年金と5種類の□□□年金のなかから選択することができます。なお、国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」 |
| Ⅱ | 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ② )円の範囲内で、500円単位で選択することができます。また、共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。このうち、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、税法上、( ③ )として所得税の課税対象となります」 |
<語句群>
イ.確定 ロ.有期 ハ.終身
ニ.30,000 ホ.55,000 ヘ.66,000
ト.68,000 チ.70,000 リ.退職所得
ヌ.一時所得 ル.雑所得
イ.確定 ロ.有期 ハ.終身
ニ.30,000 ホ.55,000 ヘ.66,000
ト.68,000 チ.70,000 リ.退職所得
ヌ.一時所得 ル.雑所得
正解:ハ、チ、リ
| ① | 国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなければなりません。 |
| ② | 小規模企業共済の掛金の拠出限度額(月額)は、最大7万円です。 |
| ③ | 小規模企業共済の共済金を死亡以外の事由で受け取る場合、分割(年金形式)で受け取った分は雑所得、一時金で受け取った分は退職所得となります。 |
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、《設例》の〈X社およびY社に関する資料〉に基づいて、株式の投資指標等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「一般に、ROEの数値が高いほうが経営の効率性が高いと判断されます。ROEは、Y社のほうがⅩ社よりも高くなっています」 |
| ② | 「株主への利益還元の大きさに着目した指標として、配当性向があります。配当性向は、X社のほうがY社よりも高くなっています。一般に、配当性向が高いほど、株主への利益還元の度合いが高いと考えることができます」 |
| ③ | 「PERやPBR等が低い銘柄など、企業の業績や財務内容等からみて株価が割安と判断される銘柄に投資する手法は、一般に、バリュー投資と呼ばれます」 |
正解:×、○、○
| ① | ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100の算式で計算されますから、 X社のROE(%)=245,000百万円÷2,100,000百万円×100=11.666…%≒11.67% Y社のROE(%)=230,000百万円÷2,700,000百万円×100=8.518…%≒8.52% となり、ROEはX社の方が高いです。 |
| ② | 正しい記述です。配当性向(%)=年間配当金総額÷当期純利益×100の算式で計算されますから、 X社の配当性向(%)=77,000百万円÷245,000百万円×100=31.428…%≒31.43% Y社の配当性向(%)=69,000百万円÷230,000百万円×100=30% となり、X社の方が配当性向が高い=株主への利益還元の度合いが高いと考えることができます。 |
| ③ | 正しい記述です。 |
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、NISAについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「NISA口座のうち、『成長投資枠』の年間投資枠は240万円であり、上場株式等の買付代金だけでなく、当該買付に係る手数料等が含まれます」 |
| ② | 「『成長投資枠』や『つみたて投資枠』の年間投資枠のうち、ある年に未使用となった分を翌年の年間投資枠に繰り越して使用することはできません」 |
| ③ | 「NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として個別銘柄指定方式を選択する必要があります」 |
正解:×、○、×
| ① | NISA口座の買付限度額は、約定金額のみ(手数料等を除く金額)で計算します。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として(NISA口座以外の口座で保有する株式に係る配当金と区別して受け取る)株式数比例配分方式を選択する必要があります。 |
【問6】
Z社債を《設例》の〈Z社債に関する資料〉に基づいて購入した場合において、次の①、②をそれぞれ求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、〈答〉は、表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。また、税金等は考慮しないものとする。
| ① | Z社債を償還まで保有した場合の最終利回り(年率・単利) |
| ② | Z社債を2年後に額面100円当たり101.80円で売却した場合の所有期間利回り(年率・単利) |
正解:0.43(%)、0.64(%)
| ① | 最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={0.9+(100-102.3)÷5}÷102.3×100=0.430…%≒0.43%となります。 |
| ② | 所有期間利回り(%)={表面利率+(売却価格-購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100={0.9+(101.8-102.3)÷2}÷102.3×100=0.635…%≒0.64%となります。 |
【問7】
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
| Ⅰ | 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿の保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高で( ② )万円となります」 |
| Ⅱ | 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( ③ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について( ④ )を選択できることなどが挙げられます」 |
<語句群>
イ.1 ロ.3 ハ.5 ニ.10
ホ.38 ヘ.48 ト.55 チ.65
リ.低価法
ヌ.個別法 ル.原価法
イ.1 ロ.3 ハ.5 ニ.10
ホ.38 ヘ.48 ト.55 チ.65
リ.低価法
ヌ.個別法 ル.原価法
正解:チ、ニ、ロ、リ
| ① | 事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除の額は、最大65万円です。 |
| ② | 期限後申告を居た場合、青色申告特別控除の額は、最大10万円となります。 |
| ③ | 青色申告者が受けられる税務上の特典のうち、純損失の繰越控除は、純損失を最大3年間繰り越して、翌年の所得と通算することができる制度です。 |
| ④ | 青色申告者は、棚卸資産を低価法により評価することができます。期末棚卸高を低く評価することにより、売上原価が増加し、所得を減少させる(ひいては、税額を減少させる)効果があります。 |
【問8】
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品として、源泉分離課税の対象となります」 |
| ② | 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に係る負債の利子30万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」 |
| ③ | 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、38万円です」 |
正解:×、○、×
| ① | 一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から5年以内に受け取ると、源泉分離課税の対象となりますが、本問のように5年を超えて受け取った場合には、一時所得として課税されます。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | Aさんの合計所得金額(分離課税される所得や、純損失の繰越控除・雑損失の繰越控除が無い場合、総所得金額と同額。具体的な計算方法は【問9】の解説の通り。)は2,400万円以下ですから、所得税の計算上、基礎控除の額は48万円となります。 |
【問9】
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
| (a)総所得金額 | ( ① )円 |
| 社会保険料控除 | □□□円 |
| 生命保険料控除 | □□□円 |
| 地震保険料控除 | □□□円 |
| 扶養控除 | ( ② )円 |
| 基礎控除 | □□□円 |
| (b)所得控除の額の合計額 | □□□円 |
| (c)課税総所得金額((a)-(b)) | 3,100,000円 |
| (d)算出税額((c)に対する所得税額) | ( ③ )円 |
| <資料>所得税の速算表 | ||
| 課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
| 195万円未満 | 5% | - |
| 195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
| 330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
| 695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
| 900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
正解:5,400,000(円)、580,000(円)、212,500(円)
| ① | 事業所得550万円は全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の赤字50万円は、土地取得のための借入金の利子相当額30万円を除く20万円が損益通算の対象となります。 終身保険の解約返戻金と契約から5年を超えて受け取る一時払変額個人年金保険の解約返戻金はどちらも一時所得の対象となりますから、一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=(460+610)万円-(500+500)万円-50万円=20万円となります。 一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額=550万円-20万円+20万円×1/2=540万円となります。 |
| ② | 長女Cさんは、16歳未満であるため、扶養控除の対象になりません。 また、母Dさんは、公的年金に掛かる雑所得(65歳以上の人は、他の所得が無い場合、公的年金等控除額110万円が最低保証される)の額が0となり、合計所得金額が48万円を下回りますから、扶養控除の計算上、老人扶養親族(同居老親等)として、58万円の控除対象となります。 よって、扶養控除の額は、58万円となります。 |
| ③ | 課税総所得金額=310万円より、速算表に当てはめると、算出税額は、3,100,000円×10%-97,500円=212,500円となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |