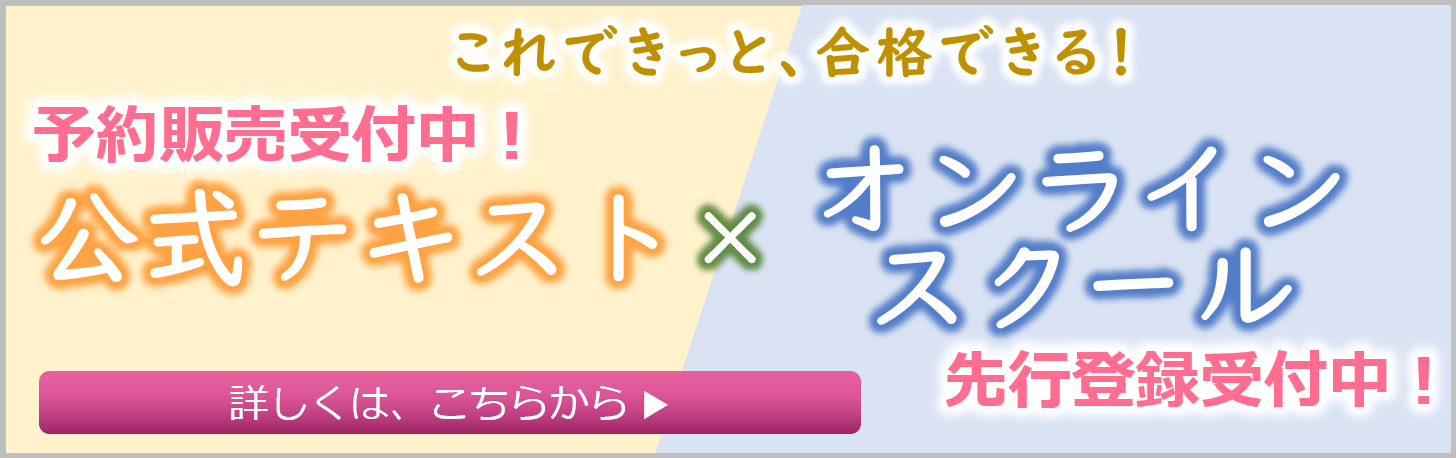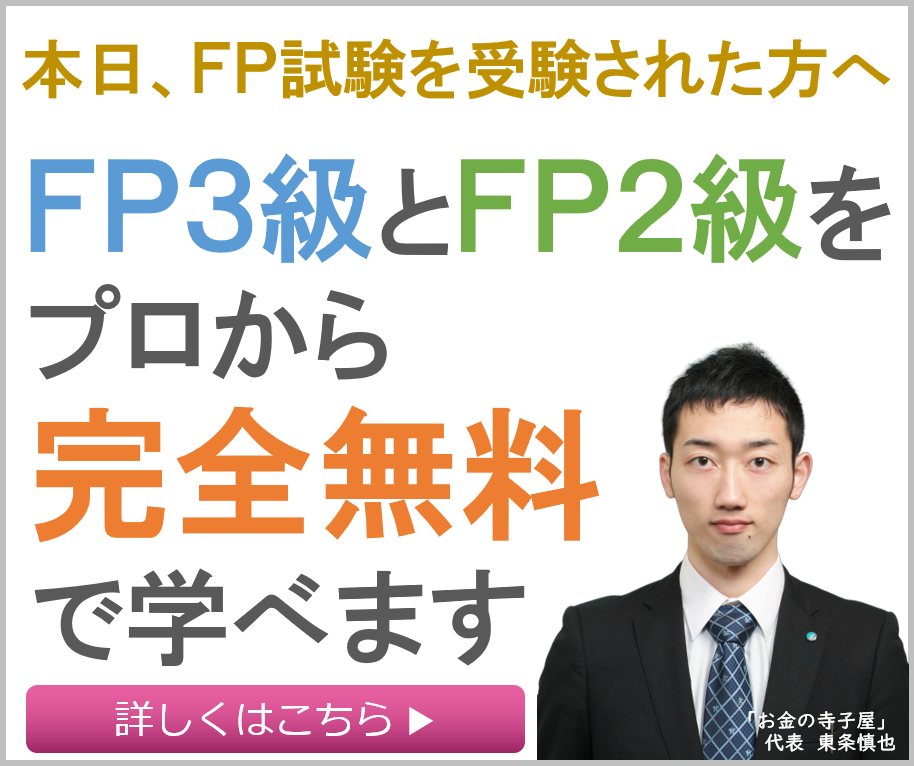FP2級実技(生保)解説-2022年5月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(48歳)は、X株式会社を2019年8月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立して約3年が経過した現在、収入は安定している。Aさんは、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

Aさん(48歳)は、X株式会社を2019年8月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立して約3年が経過した現在、収入は安定している。Aさんは、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(個人事業主)]
| 1973年8月11日生まれ(48歳) | |
| 公的年金加入歴: | 下図のとおり(60歳までの見込みを含む) |

[妻Bさん(会社員)]
| 1972年10月29日生まれ(49歳) | |
| 公的年金加入歴: | 20歳から22歳の大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(325月)は厚生年金保険に加入している。妻Bさんは、65歳になるまで厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。 |
| ※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
| ※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
| ① | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額 |
| ② | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額 |
<資料>


正解:728,840、599,799
| ① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の保険料納付済期間と厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、国民年金未加入期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=780,900円×(84+197+167)/480=728,840円となります。 |
| ② | 報酬比例部分の額=28万円×7.125/1,000×84+40万円×5.481/1,000×197=599,482.8円≒599,483円となります。 経過的加算額=1,628円×(84+197)-780,900円×(84+197)/480=316.125円≒316円となります。 また、年上の配偶者がいる場合には、加給年金は支給されませんから、老齢厚生年金の年金額は、599,483円+316円=599,799円となります。 |
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は保証期間のある( ① )年金A型、保証期間のない( ① )年金B型の2種類のなかから選択します。掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入時の年齢等で決まり、掛金の拠出限度額は月額( ② )円となります。なお、( ③ )に加入している場合は、その掛金と合わせて月額( ② )円が上限となります」
<語句群>
イ.23,000 ロ.68,000 ハ.70,000
ニ.有期 ホ.確定 ヘ.終身
ト.小規模企業共済制度
チ.確定拠出年金の個人型年金
リ.中小企業退職金共済制度
イ.23,000 ロ.68,000 ハ.70,000
ニ.有期 ホ.確定 ヘ.終身
ト.小規模企業共済制度
チ.確定拠出年金の個人型年金
リ.中小企業退職金共済制度
正解:ヘ、ロ、チ
| ① | 国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選びます。 |
| ② | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。 |
| ③ | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の拠出限度額と枠を共有します。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「国民年金の付加保険料を納付することで、老後の年金収入を増やすことができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」 |
| ② | 「国民年金基金の1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」 |
| ③ | 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。Aさんが支払った掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」 |
正解:×、○、×
| ① | 付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加保険料納付月数が120月である場合、付加年金の額は200円×120=24,000円です。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | 個人が拠出した小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象となります。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(61歳)は、専業主婦である妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは、現在加入している生命保険を介護保障が充実したプランに見直したいと考えているが、これまで生命保険の見直しをしたことがなく、見直しの方法等わからないことが多い。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(61歳)は、専業主婦である妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは、現在加入している生命保険を介護保障が充実したプランに見直したいと考えているが、これまで生命保険の見直しをしたことがなく、見直しの方法等わからないことが多い。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類:定期保険特約付終身保険
契約年月日:2006年8月1日
月払保険料:22,700円(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

保険の種類:定期保険特約付終身保険
契約年月日:2006年8月1日
月払保険料:22,700円(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、必要保障額および現在加入している定期保険特約付終身保険の保障金額について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①、②に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「介護保障を充実させる前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は( ① )万円となります。Aさんが現時点で死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、定期保険特約付終身保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( ② )万円となります。他方、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は□□□万円となります」
<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
| <条件> | |
| 1. | 現在の毎月の日常生活費は35万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費の50%とする。 |
| 2. | 現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、30年とする。 |
| 3. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)、緊急予備資金は、500万円とする。 |
| 4. | 住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、300万円とする。 |
| 5. | 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,200万円とする。 |
| 6. | Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,500万円とする。 |
| 7. | 現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。 |
正解:100、1,500
| ① |
生活費:35万円/月×50%×12月×30年=6,300万円 また、 したがって、必要保障額=6,800万円-6,700万円=100万円となります。 |
| ② | 終身保険200万円+定期保険特約1,100万円+特定疾病保障定期保険特約200万円=1,500万円です。 |
【問5】
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」 |
| ② | 「公的介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られていますが、第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができます」 |
| ③ | 「公的介護保険の第1号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」 |
正解:○、○、×
| ① | 正しい記述です。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | 公的介護保険の第1号被保険者の自己負担割合は、所得の額に応じて1割~3割です。 |
【問6】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現在加入している生命保険の見直し等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「現在加入している定期保険特約付終身保険の定期保険特約は、65歳の主契約の保険料払込期間満了後も更新することができますが、更新後の保険料は大幅に上昇します。支出可能な保険料の額を踏まえたうえで、無理のない範囲内で見直しを行ってください」 |
| ② | 「現在加入している終身保険を残し、その他の特約を減額または解約して、介護保険に新規加入する方法が考えられます。公的介護保険の給付は、主に訪問介護や通所介護(デイサービス)などの現物給付による介護サービスであるため、一定額の介護年金および介護一時金を準備することは検討に値すると思います」 |
| ③ | 「現在加入している定期保険特約付終身保険を見直す方法として、契約転換制度の活用が考えられます。契約転換時の告知や医師の診査は不要で、健康状態にかかわらず、保障内容を見直すことができます」 |
| ④ | 「現在加入している定期保険特約付終身保険を契約転換して、同じ生命保険会社の介護保障に特化した保険に加入した場合、現在加入している終身保険の保障は消滅します。契約転換制度を利用する際は、転換前・転換後契約の保障内容等を比較して、総合的に判断してください」 |
正解:×、○、×、○
| ① | 保険料の払込満了期間が満了すると、特約を更新することができなくなります。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | 転換は、保険契約の乗り換え(解約後の再契約)のようなものですから、契約の転換を行う際には、告知または医師の診査が必要です。 |
| ④ | 正しい記述です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(55歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。X社は、近年、売上金額・利益金額ともに減少傾向にある。X社は、今後の保険料負担も考慮し、現時点において下記<資料>の生命保険契約を解約しようと考えている。 そこで、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(55歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。X社は、近年、売上金額・利益金額ともに減少傾向にある。X社は、今後の保険料負担も考慮し、現時点において下記<資料>の生命保険契約を解約しようと考えている。 そこで、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<資料>解約を検討中の生命保険の契約内容
保険の種類:5年ごと利差配当付定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2007年7月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡保険金額:1億円
年払保険料:200万円
現時点の解約返戻金額:2,700万円(単純返戻率90.0%)
65歳時の解約返戻金額:4,700万円(単純返戻率94.0%)
※保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
※単純返戻率=解約返戻金額÷払込保険料累計額×100
保険の種類:5年ごと利差配当付定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2007年7月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡保険金額:1億円
年払保険料:200万円
現時点の解約返戻金額:2,700万円(単純返戻率90.0%)
65歳時の解約返戻金額:4,700万円(単純返戻率94.0%)
※保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
※単純返戻率=解約返戻金額÷払込保険料累計額×100
| ※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を28年9カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
| ① | 退職所得控除額 |
| ② | 退職所得の金額 |
正解:1,430、1,785
| ① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の一年未満の端数は切り上げます。 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円より、退職所得控除額=70万円×(29-20)+800万円=1,430万円となります。 |
| ② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,430万円)×1/2=1,785万円となります。 |
【問8】
《設例》の生命保険を現時点で解約した場合のX社の経理処理(仕訳)について、下記の<条件>を基に、空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
| <条件> | |
| ・ | X社が解約時までに支払った保険料の総額は3,000万円である。 |
| ・ | 解約返戻金の金額は2,700万円である。 |
| ・ | 配当等、上記以外の条件は考慮しないものとする。 |
<解約返戻金受取時のX社の経理処理(仕訳)>


<語句群>
イ.150 ロ.300 ハ.1,200
ニ.1,350 ホ.1,500 ヘ.1,650
ト.2,700
チ.3,000 リ.雑収入
ヌ.雑損失 ル.保険料積立金
イ.150 ロ.300 ハ.1,200
ニ.1,350 ホ.1,500 ヘ.1,650
ト.2,700
チ.3,000 リ.雑収入
ヌ.雑損失 ル.保険料積立金
正解:ト、ホ、リ、ハ
| ① | 解約返戻金の金額は2,700万円であることから、現金・預金は2,700万円増えます。 |
| ② | 2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。 よって、現時点の払込保険料累計額が3,000万円であるということは、資産計上額が1,500万円であると推定されます。 |
| ③ | 資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である1,500万円と解約返戻金2,700万円との差額である1,200万円を、雑収入として処理します。 |
| ④ | ③の通りです。 |
【問9】
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
| ① | 「解約を検討中の生命保険について、解約をせず、払済終身保険に変更することも検討事項の1つとなります。現時点で払済終身保険に変更した場合であっても、65歳時の解約返戻金額は4,700万円が確保されます」 |
| ② | 「経営者が要介護状態あるいは重度の疾患等で長期間不在となった場合、業績が悪化することが想定されます。既契約の加入状況を確認したうえで、Aさんが重い病気等になった場合にX社が一時金(現金)を受け取ることができる生前給付タイプの生命保険に新規加入することもご検討ください」 |
| ③ | 「Aさんが死亡した場合の1億円の事業保障資金の準備のみを目的とするのであれば、現在加入している生命保険よりも保険料が割安となる保険期間が10年の定期保険に新規加入する方法もあります」 |
正解:×、○、○
| ① | 払済保険は、現在の解約返戻金を元に新しい保険に切り替える制度ですから、元の契約で貰えるはずであった解約返戻金を確保することはできなくなります。 |
| ② | 正しい記述です。 |
| ③ | 正しい記述です。死亡保障の準備のみを目的として加入するのであれば、解約返戻金のない定期保険の方が、解約返戻金のある定期保険よりも保険料が割安になり、合理的な選択だと言えます。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |