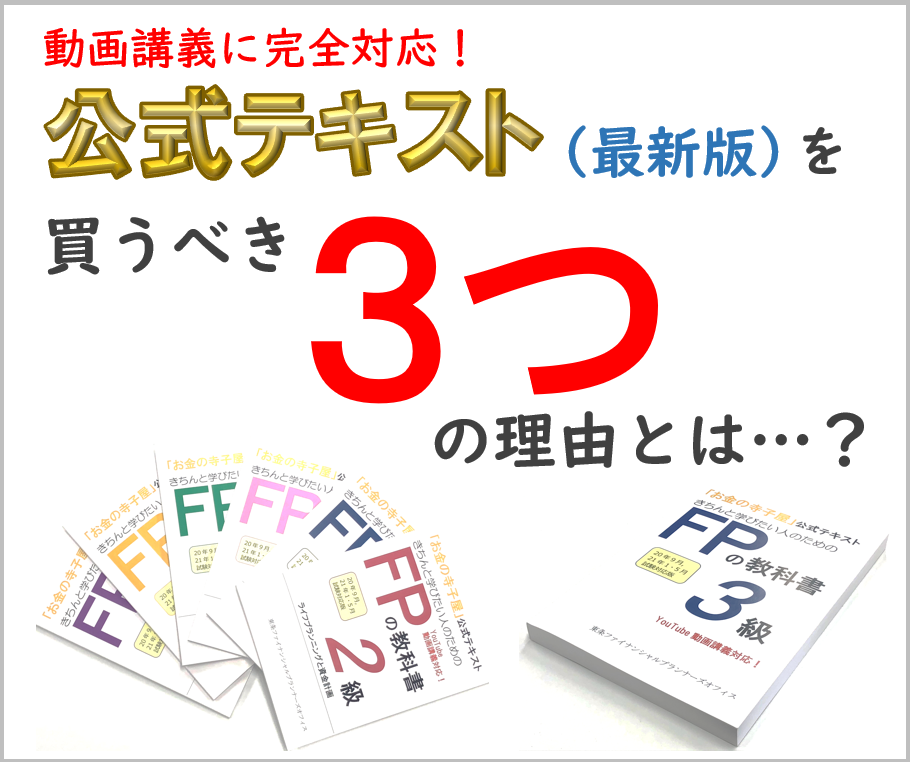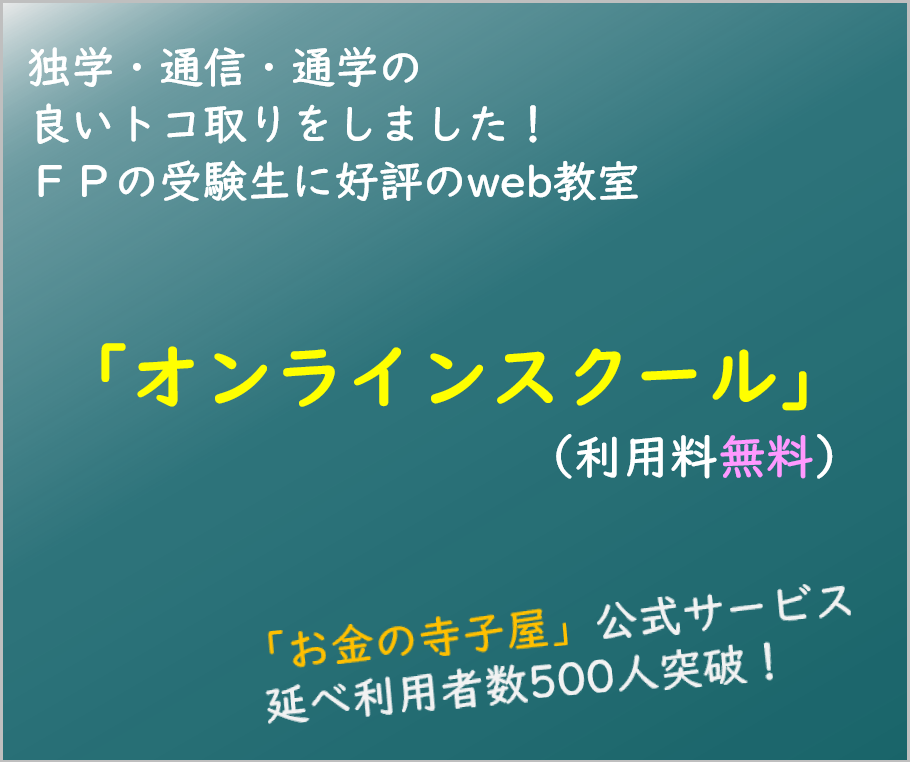正誤問題(FP2) 介護保険・労災保険・雇用保険(2/2)
2025.6~2026.5試験対応済み
【問13】★
雇用保険の保険料は、労使折半で納める。
【答13】
×:雇用保険の保険料は、事業主負担が少し多いです。
【問14】★
雇用保険の窓口は、労働基準監督署である。
【答14】
×:雇用保険の窓口は、公共職業安定所(ハローワーク)です。
【問15】★
雇用保険の基本手当の受給要件は、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間がある事等である。
【答15】
○:正しい記述です。なお、自己都合以外の事由(倒産・解雇・雇止め等)による退職の場合、要件が緩和され、離職の日以前1年間に6ヵ月以上の被保険者期間がある事等とされます。
【問16】★
雇用保険の基本手当の支給開始までには、求職の申込から7日間の待機期間があり、さらに、正当な理由のない自己都合退職者は、最長2ヵ月間の給付制限期間がある。
【答16】
×:雇用保険の基本手当の待機期間は7日、給付制限期間は基本的に1ヵ月(最長で3ヵ月)です。
【問17】★
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。
【答17】
○:雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間です。
【問18】
雇用保険の基本手当の受給期間は、病気やケガ、妊娠、出産などのやむを得ない事情がある場合、申請すると、最長4年間とする事が出来る。
【答18】
○:基本手当の受給期間は、一定要件を満たした場合、3年間延長して、1年(本来の受給期間)+3年(延長期間)=4年とする事ができます。
【問19】★
雇用保険の基本手当は、雑所得として所得税の課税対象となる。
【答19】
×:雇用保険の基本手当は、非課税です。
【問20】
雇用保険の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に安定した職業に就いた場合、再就職手当として、基本手当日額に基本手当の支給残日数の50%または60%をかけた金額が支給される。
【答20】
×:再就職手当は、基本手当日額に基本手当の支給残日数の60%または(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合)70%を掛けた金額となります。
【問21】
雇用保険の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に安定した職業に就いた場合、再就職手当として、基本手当日額に基本手当の支給残日数の50%または60%をかけた金額が支給される。
【答21】
×:再就職手当は、基本手当日額に基本手当の支給残日数の60%または(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合)70%を掛けた金額となります。
【問22】
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、どちらも最高で現在支給されている賃金の15%が支払われる。
【答22】
○:高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の支給率は、どちらも最高10%(賃金の低下率が64%以下となった場合)です。
【問23】★
一般教育訓練給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間の要件は、2年以上とされている。
【答23】
×:一般教育訓練給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間の要件は、3年以上(初めて支給を受ける人は1年以上)です。
【問24】
一般教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った教育訓練費の20%(最高10万円)が支給されるものである。
【答24】
○:なお、支給額は最低4,000円です(2万円以上の訓練費の講座を受講しなければ、教育訓練給付金は支払われません)。
【問25】★
育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
【答25】
○:育児休業給付金の支給額は、休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間あたり、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額です。
なお、育児休業の開始から181日目以降は、支給率が50%になります。
なお、育児休業の開始から181日目以降は、支給率が50%になります。
【問26】★
育児休業給付金は、1支給単位期間において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の75%以上の賃金が支払われている場合、支給されない。
【答26】
×:育児休業給付金は、1支給単位期間において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上の賃金が支払われている場合、支給されません。
【問27】★
被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
【答27】
×:育児休業を分割して取得した場合、原則として、2回まで育児休業給付が支給され、3回目以降の育児休業については支給されません。
【問28】★
雇用保険の一般被保険者の父母および配偶者の父母は、どちらも、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
【答28】
○:正しい記述です。介護休業給付金の支給対象となる人は、事実婚や養子縁組を含めて考えて、2親等以内の血族と、1親等以内の姻族です。よって、被保険者の父母(1親等の血族)と被保険者の配偶者の父母(1親等の姻族)は、どちらも対象となります。
【問29】★
介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
【答29】
×:介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに3回を限度として支給されます。
【問30】
介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%相当額である。
×:介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額です。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | 一覧へ |