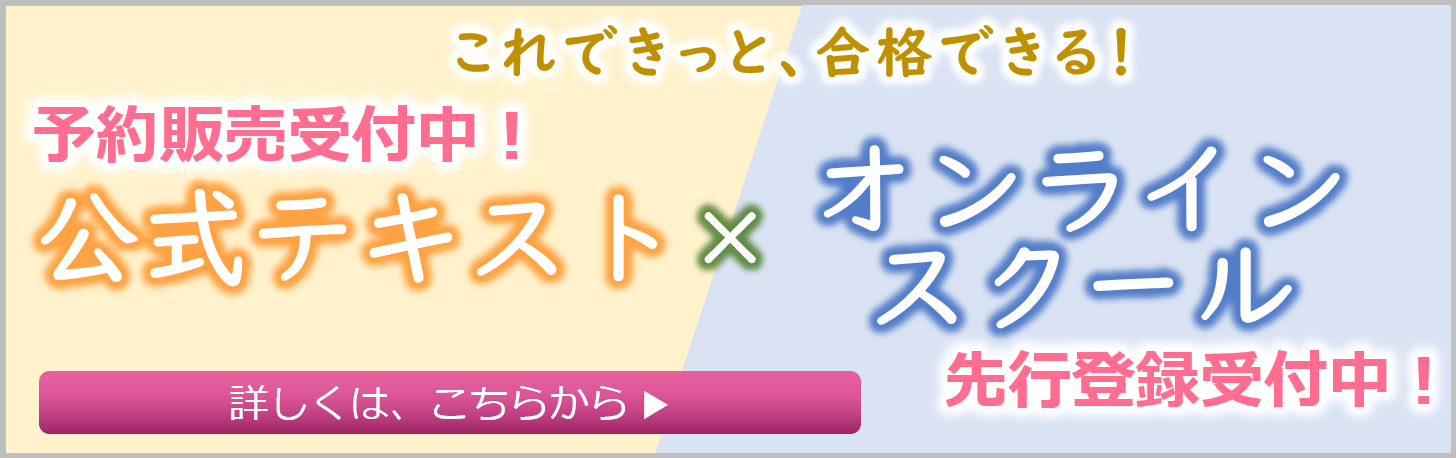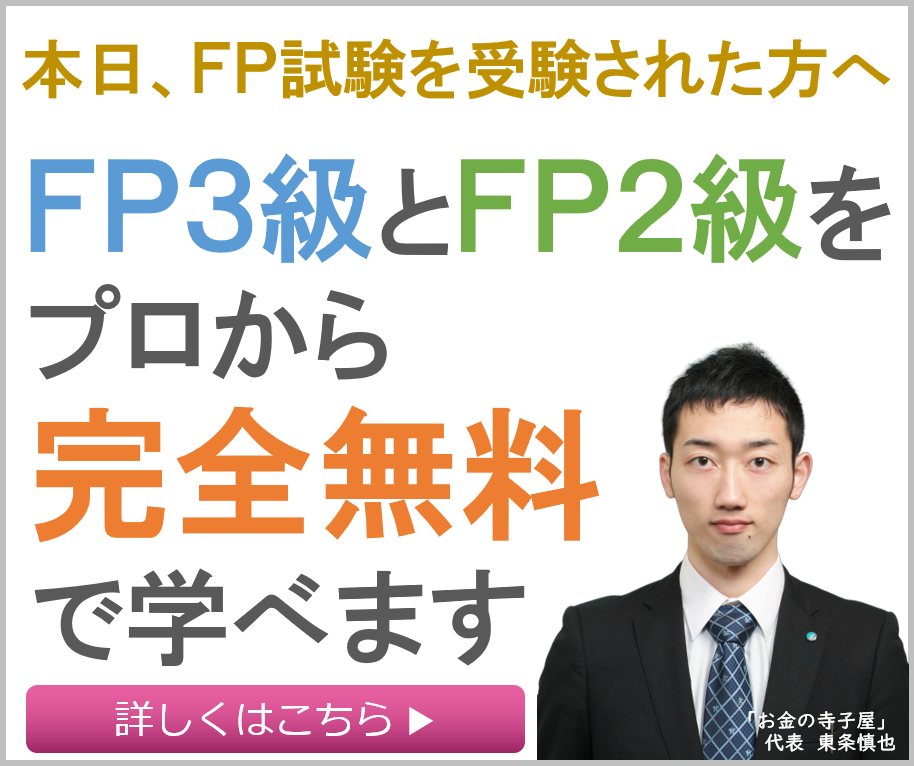FP2級学科解説-2025年1月・問1~10
【問1】
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
| 1. | 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。 |
| 2. | 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。 |
| 3. | 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。 |
| 4. | 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 公的年金の個別具体的な受給見込み額の計算は、有償・無償を問わず、誰でもすることができます。 |
| 2. | 個別具体的な税額の計算や確定申告書のような税務書類の作成を代行は、税理士の登録を受けた人しかすることができませんません。 |
| 3. | 具体的な銘柄・数量・時期を指定した有償での投資助言は、金融商品取引業者の登録を受けた人しかすることができませんません。 |
| 4. | 弁護士または弁護士法人でない人が、報酬を得る目的で、訴訟事件や法律事件(紛争が発生している事案や、将来的に紛争が発生する可能性がある事案)について、代理や仲裁などの法律事務を業として行うことは認められていません。 |
【問2】
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。 |
| 2. | 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。 |
| 3. | 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。 |
| 4. | 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。協会けんぽの保険料率は、一般保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。 |
| 2. | 正しい記述です。、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象外です。 |
| 3. | 正しい記述です。任意継続被保険者となることができる期間は、最長2年間です。 |
| 4. | 出産育児一時金と家族出産育児一時金は併給されません。本人(女性の被保険者)が出産した場合に支払われるのが出産育児一時金、被保険者の被扶養者が出産した場合に支払われるのが家族出産育児一時金だからです。 |
【問3】
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。 |
| 2. | 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。 |
| 3. | 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。 |
| 4. | 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 正しい記述です。複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者について、2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間未満である事業所は除きます)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である場合、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。この制度を雇用保険マルチジョブホルダー制度と言います。 |
| 2. | 失業等給付と育児休業給付に係る保険料は、労使折半で負担し、雇用保険二事業に係る保険料は、全額事業主が負担します。 |
| 3. | 一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日です。 |
| 4. | 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業181日目以降は50%)です。 |
【問4】
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。 |
| 2. | 老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。 |
| 3. | 老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。 |
| 4. | 加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 老齢年金を繰下げると、1月あたり0.7%増額されます。 |
| 2. | 66歳になる前に障害給付や遺族給付を受け取る権利がある人は、原則として、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げをすることができません。 但し、障害基礎年金のみ受給権がある人は、老齢厚生年金の繰下げをすることができます。 |
| 3. | 公的年金を繰下げる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げる(片方だけ繰下げる場合を含む)ことができます。 なお、繰上げる場合は、同時に繰上げなくてはなりません。 |
| 4. | 老齢厚生年金を繰下げた場合、その期間中の期間中は加給年金は支給停止されます。また、繰下げ受給後に受け取る加給年金が増額されることもありません。 |
【問5】
確定拠出年金の企業型年金を新たに導入する際の既存の退職金制度等との関係等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について都道府県知事の承認を受ける必要がある。 |
| 2. | 退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することができる。 |
| 3. | 確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。 |
| 4. | 中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできない。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。 |
| 2. | 退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で移管することはできず、4~8年で均等に移管しなければなりません。 |
| 3. | 正しい記述です。通算加入者等期間とは、確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間のうち、加入者期間と運用指図期間を合算した期間を言いますが、他の企業年金制度等から確定拠出年金に移換した資産がある場合は、その移換資産の算定の基礎となる期間も合算されます。 |
| 4. | 中小企業退職金共済に加入している企業が共済契約を解除する場合、基本的に、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできませんが、中小事業者でなくなった場合等は、移管することができます。 |
【問6】
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
| 1. | 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。 |
| 2. | 常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。 |
| 3. | 中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。 |
| 4. | 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 国民年金の任意加入被保険者は、基本的に、1号被保険者に準じた扱いを受けるため、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができます。 |
| 2. | 正しい記述です。中退共の加入資格は、基本的に、常時使用する従業員の数が20人(商業(卸売業・小売業)、宿泊業・娯楽業を除くサービス業を営む場合は5人)以下の個人事業主または会社の役員とされています。 |
| 3. | 正しい記述です。中小企業退職金共済の掛金は、被共済者1人当たり5,000円から30,000円の範囲内で設定し、事業主が全額負担します。 |
| 4. | 正しい記述です。中小企業退職金共済の退職金は、退職日に60歳以上であり、分割払対象額(併用払いの場合は一時金払対象額も)が一定額以上あれば、5年または10年間にわたって分割して受け取ることができます。 なお、退職日の年齢が60歳未満の場合は、一時金払い(一括払い)しか認められません。 |
【問7】
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。 |
| 2. | 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 |
| 3. | 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。 |
| 4. | 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額損金算入することができます。 |
| 2. | 小規模企業共済等掛金控除は、本人分の拠出額のみが対象となります。 |
| 3. | 正しい記述です。中退共の掛金は、法人は全額損金算入、個人事業主は全額必要経費に算入することができます。 |
| 4. | 個人事業主が拠出した規模企業共済の掛金は、事業所得の計算上の必要経費ではなく、所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)となります。 |
【問8】
日本学生支援機構の奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。 |
| 2. | 日本学生支援機構の奨学金の対象となる学校は、国内に所在する大学等に限られ、海外に所在する大学等は対象とならない。 |
| 3. | 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。 |
| 4. | 国の教育ローンの資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。入学時特別増額貸与奨学金は、入学した月の分の奨学金の月額に、10万円から50万円までの額(10万円刻み)で希望する額を上乗せして貸与される奨学金です。 なお、国の教育ローンを利用することができなかった世帯の学生・生徒向けの制度ですから、国の教育ローンと併用することはできません。 |
| 2. | 日本学生支援機構の奨学金には、海外留学のための奨学金もあります。 |
| 3. | 正しい記述です。国の教育ローンを利用するためには、世帯で扶養している子の人数に応じて定められた世帯年収(所得)の要件があります。 |
| 4. | 正しい記述です。国の教育ローンの資金使途は、幅広く認められています。 |
【問9】
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。 |
| 2. | 老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。 |
| 3. | 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。 |
| 4. | 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 正しい記述です。一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本(取崩型運用の現在の金額)を求めるためには、年金現価係数(6文字、「げん」の音がある、「年金」がつくの3要件を満たす係数)を使います。 |
| 3. | 正しい記述です。任意後見契約は、必ず、公正証書によって締結しなければなりません。 |
| 4. | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、70歳までの雇用確保のため、定年の引き上げ、定年制の廃止、継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入など、所定の措置を講じるよう努めなければならないことを定めた法律です。 |
【問10】
キャッシュレス決済の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | クレジットカードは、原則として、カード会社が設定した利用枠(利用限度額)内で、商品やサービスを受け取った後に支払請求がされる後払いの決済手段である。 |
| 2. | クレジットカードで商品やサービスを購入した場合の返済方法の一つである分割払いは、利用代金の支払回数を決め、その回数で代金を分割して支払う方法である。 |
| 3. | デビットカードで商品やサービスを購入した場合、クレジットカードと同様に、定額リボルビング払いや分割払いで代金の支払いをすることができる。 |
| 4. | 交通系や流通系の電子マネーやプリペイドカードは、カードやスマートフォンに事前にチャージしておき、商品やサービスの購入時にチャージ額から支払う決済手段である。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。クレジットカードを利用すると、利用限度額内で、商品やサービスを購入することができ、一定期間における利用額が、後日決められた日にまとめて請求されます(後払い)。 |
| 2. | 正しい記述です。クレジットカードで商品やサービスを購入した場合の返済方法には、一括払い、分割払い、リボ払いがあります。 分割払いは、利用代金を指定した回数で均等に分割して支払う方法で、リボ払いは、毎回一定の金額を利用代金の残額が0になるまで支払う方法です。 |
| 3. | デビットカードで商品やサービスを購入した場合、即時に、銀行口座から商品代金が引き落とされます(即時払い)。 |
| 4. | 正しい記述です。交通系や流通系の電子マネーやプリペイドカードは、前払方式の決済手段です。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |