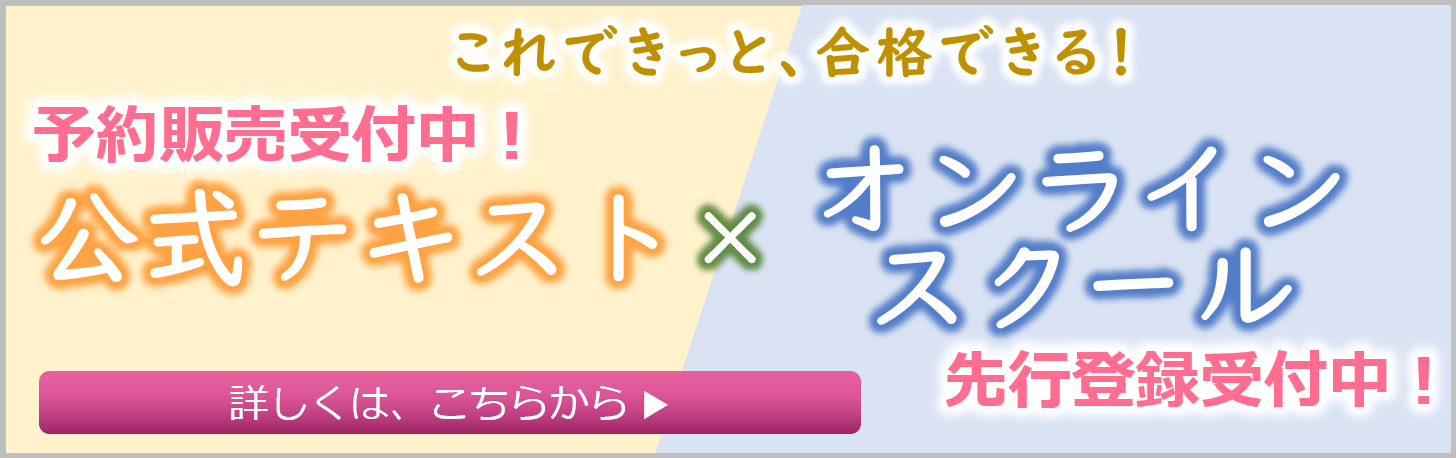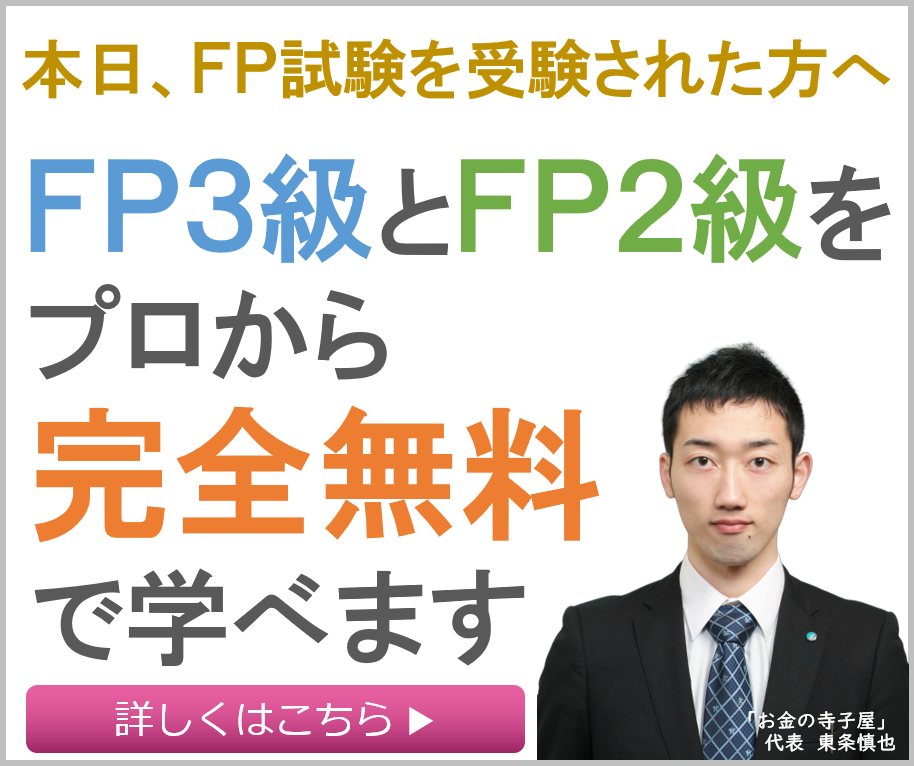FP2級実技(FP協会)解説-2024年9月・問1~10
【問1】
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
| (ア) | 弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得る目的で顧客の起こした自動車事故の交渉代理人となり、過去の判例を引用し、法律的な判断に基づく相手方との示談交渉を代行した。 |
| (イ) | 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行った。 |
| (ウ) | 税理士の登録を受けていないFPが、生前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業務において、贈与税に関する一般的な税法の説明と仮定の事例を用いた税額の計算方法を解説した。 |
| (エ) | 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類の作成を代行し、申請手続きは顧客自身が行った。 |
正解:×、×、○、×
| (ア) | 弁護士の登録を受けていない人は、報酬を得る目的で、法律相談や法律事務を行ってはいけません。 |
| (イ) | 投資助言・代理業の登録を受けていない人は、顧客と投資顧問契約を締結して具体的な助言を行ってはいけません。 |
| (ウ) | 一般的な税法の説明や、仮定の事例を用いた税額の計算方法の解説は、有償無償を問わず、誰でもすることができます。 |
| (エ) | 社会保険関係の書類の作成や手続きの代行は、社会保険労務士の登録を受けていない人が行ってはいけません。 |
【問2】
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。 |
| 2. | 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。 |
| 3. | 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。 |
| 4. | 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。 |
正解:1
| 1. | 正しい記述です。 |
| 2. | 消費者契約の取消権は、基本的に、追認することができる時(誤認していたことに気付いた時や困惑の状態を脱した時など)から、1年間行使しない場合、または、当該消費者契約の締結時から5年を経過した場合は、時効により消滅します。 |
| 3. | 事業者の軽過失により生じた事業者の責任の一部を免除する条項については、軽過失の場合にのみ適用されることを明記する表現にしなければ、その条項が無効になります。 「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という表現は、法律的には、「軽過失の場合は、5万円を上限として賠償する」という意味として解釈されますが、法律に詳しくない消費者が正しく解釈できず権利行使を思いとどまってしまう可能性があることから、事業者の軽過失により生じた事業者の責任の一部を免除する条項については、軽過失の場合にのみ適用されること(故意または重大な過失を除いて免除される旨)を明記する表現にしなければ、その条項が無効になります。 |
| 4. | 消費者の解除権を放棄させる条項は、無効になります。 |
【問3】
浅見さんはQA投資信託を新規募集時に100万口購入し、特定口座(源泉徴収選択口座)で保有して収益分配金を受け取っている。下記<資料>に基づき、浅見さんが保有するQA投資信託に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
[QA投資信託の商品概要(新規募集時)]
| 投資信託の分類 | : | 追加型国内公募株式投資信託 |
| 決算および収益分配 | : | 年1回 |
| 申込価格 | : | 1口当たり1円 |
| 申込単位 | : | 1万口以上1口単位 |
| 購入時手数料(税込み) | : | 購入金額1,000万円未満 購入金額に対し3.30% 購入金額1,000万円以上 購入金額に対し2.20% |
| 購入時手数料 (税込み) |
: | 購入金額1,000万円未満 購入金額に対し3.30% 購入金額1,000万円以上 購入金額に対し2.20% |
| 運用管理費用(信託報酬)(税込み) | : | 純資産総額に対し年1.760% |
| 運用管理費用(信託報酬)(税込み) | : | 純資産総額に対し 年1.760% |
[浅見さんが保有するQA投資信託の収益分配金受取時の運用状況(1万口当たり)]
収益分配前の個別元本:9,200円
収益分配前の基準価額:10,000円
収益分配金:1,000円
収益分配後の基準価額:9,000円
| ・ | 浅見さんが、QA投資信託を新規募集時に100万口購入した際に、支払った購入時手数料(税込み)は、( ア )である。 |
| ・ | 収益分配時に、浅見さんに支払われた収益分配金のうち、普通分配金(1万口当たり)は( イ )である。 |
| 1. | (ア)22,000円 (イ)200円 |
| 2. | (ア)22,000円 (イ)800円 |
| 3. | (ア)33,000円 (イ)200円 |
| 4. | (ア)33,000円 (イ)800円 |
正解:4
| (ア) | 新規募集時(1口=1円の時)に100万口購入すると、購入金額は100万円となります。 資料より、購入金額が1,000万円未満の場合、適用される手数料率は3.30%ですから、支払った購入時手数料は、100万円×3.30%=33,000円となります。 |
| (イ) | 収益分配前の基準価額が10,000円、収益分配後の基準価額が9,000円ですから、分配金1,000円のうち、個別元本(9,200円)を上回る部分(普通分配金)は800円です。 |
【問4】
安藤さんと井川さんは、下記<資料>のとおり、QT株式会社の株式(以下「QT株式」という)を2024年1月から同年5月において毎月15日に購入した。安藤さんと井川さんのQT株式の取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、このほかにQT株式の取引はないものとし、手数料および税金は考慮しないものとする。また、購入株数は正しいものとする。
| ・ | 安藤さんは株式累積投資制度で購入した。 |
| ・ | 井川さんは購入の都度、単元未満株投資制度で購入した。 |
| ・ | QT株式の1単元は100株である。 |
| ・ | QT株式会社の本決算および議決権の基準日は3月末日である。 |
| ・ | QT株式の期末株主配当金は、1株当たり100円であった。 |
<資料:QT株式の購入株価等の推移>




| 1. | 安藤さんの平均購入単価は、井川さんの平均購入単価よりも低くなっている。 |
| 2. | 安藤さんは、2024年3月に保有株式を指値注文で売却することができるが、井川さんは、2024年3月に保有株式を指値注文で売却することはできない。 |
| 3. | 安藤さんおよび井川さんは、2024年3月期の期末株主配当金を受け取ることができる。 |
| 4. | 安藤さんおよび井川さんは、2024年に開催される定時株主総会の議決権を持たない。 |
正解:2
| 1. | 正しい記述です。 安藤さんの平均購入単価=80,000円×5÷(22+20.6+25.4+22.3+21.9)=3,565.06…円です。 井川さんの平均購入単価=(79,860+85,360+69,300+78,760+80,300)円÷(22×5)=3,578円です。 |
| 2. | 保有株式を指値注文で売却するためには、単元株数以上の株式(100株以上の株式)を保有しておかなくてはなりません。 2024年3月時点で、安藤さん、井川さん共に、保有株数が100株に満たないため、2人とも保有株式を指値注文で売却することはできません。 |
| 3. | 正しい記述です。2024年3月時点で、安藤さん、井川さん共に、保有株数が100株に満たないですが、単元未満の株式についても、配当金は支払われます。 |
| 4. | 正しい記述です。議決権は、単元株数ごとに与えられますから、2024年3月時点で保有株数が100株に満たない安藤さんと井川さんは、2人とも2024年に開催される定時株主総会の議決権を持ちません。 |
【問5】
下記<資料>の特定口座(源泉徴収選択口座)で保有する外国債券(ゼロクーポン債)について、償還時の償還金額の円貨受取額を計算しなさい。なお、計算結果について円未満の端数が生じる場合は切り捨てること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
| <資料> | |||||||||||||
| ・ | 米国国債(ゼロクーポン債) | ||||||||||||
| ・ | 購入額面:10,000米ドル | ||||||||||||
| ・ | 購入単価:90(額面100当たりの価格) | ||||||||||||
| ・ | 為替レート(1米ドル)
|
||||||||||||
| ※ | 償還に際して、円貨換算した償還差益の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとする。 | ||||||||||||
正解:1,445,800(円)
ゼロクーポン債ですから、米ドルベースの取引に着目すれば、9,000米ドルで債券を買い、利息は支払われず、満期時に10,000米ドルを受け取っています。
購入時の円ベースの金額は、9,000米ドル×141円/米ドル(TTS)=1,269,000円です。
また、償還時の円ベースの金額は、10,000米ドル×149円/米ドル(TTB)=1,490,000円です。
よって、円ベースの利益は、1,490,000円-1,269,000円=221,000円ですから、源泉徴収される税金は、221,000円×20%=44,200円となります。
したがって、償還時の償還金額の円貨受取額は、1,490,000円-44,200円=1,445,800円となります。
購入時の円ベースの金額は、9,000米ドル×141円/米ドル(TTS)=1,269,000円です。
また、償還時の円ベースの金額は、10,000米ドル×149円/米ドル(TTB)=1,490,000円です。
よって、円ベースの利益は、1,490,000円-1,269,000円=221,000円ですから、源泉徴収される税金は、221,000円×20%=44,200円となります。
したがって、償還時の償還金額の円貨受取額は、1,490,000円-44,200円=1,445,800円となります。
【問6】
財形貯蓄制度に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。


<語群>
1.3 2.5 3.7 4.50
5.55 6.60 7.65
8.500
9.550 10.600
1.3 2.5 3.7 4.50
5.55 6.60 7.65
8.500
9.550 10.600
正解:5、9、6、2
| (ア) | 財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄の契約は、満55歳未満の人でなければすることができません。 |
| (イ) | 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の非課税限度額は、合算で550万円まで(貯蓄型は元利合計、保険型は払込保険料ベース)です。 |
| (ウ) | 財形年金貯蓄の受取開始は、満60歳以降です。なお、積み立て終了から年金受け取り開始まで、5年以内の据え置き期間を設定することができます。 |
| (エ) | >財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄の目的外の払い出しを行った場合、貯蓄型については、過去5年間に支払われた利息について遡及課税されます。 |
【問7】
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>




正解:130
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その敷地の建蔽率の上限は、各用途地域の建蔽率をそれぞれの敷地に占める面積の割合で加重平均した値となります。
よって、建蔽率の上限は、60%×150㎡/200㎡+80%×50㎡/200㎡=65%となります。
したがって、建築面積の最高限度は、200㎡×65%=130㎡となります。
<別解>
準住居地域部分の建築面積の最高限度は、150㎡×6/10=90㎡、近隣商業地域部分の建築面積の最高限度は、50㎡×8/10=40㎡ですから、この敷地の建築面積の最高限度は、90㎡+40㎡=130㎡となります。
(全体で130㎡以下であれば、準住居地域部分の建築面積が90㎡を超えたり、近隣商業地域部分の建築面積が40㎡を越えたりしても構いません。)
【問8】
鶴見さんは、FPで税理士でもある榎田さんに不動産に係る固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
| 鶴見さん | : | 「固定資産税について、教えてください。」 |
| 榎田さん | : | 「固定資産税は、( ア )が、毎年( イ )現在の土地や家屋などの所有者に対して課す税金です。」 |
| 鶴見さん | : | 「固定資産税には、住宅用地についての特例があると聞いています。」 |
| 榎田さん | : | 「一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)には、住宅1戸当たり( ウ )以下の部分について、課税標準額を固定資産税評価額の( エ )とする特例があります。」 |
<語群>
1.国 2.都道府県
3.市町村(東京23区は都)
4.1月1日 5.4月1日
6.200㎡
7.240㎡ 8.3分の1 9.6分の1
1.国 2.都道府県
3.市町村(東京23区は都)
4.1月1日 5.4月1日
6.200㎡
7.240㎡ 8.3分の1 9.6分の1
正解:3、4、6、9
| (ア) | 固定資産税の課税主体は、市町村(東京23区は都)です。 |
| (イ) | 固定資産税は、毎年1月1日現在において、課税対象となる固定資産の所有者に対して課されます。 |
| (ウ) | 固定資産税の小規模住宅用地の特例の適用を受けると、200㎡までに係る課税標準が6分の1になります。 |
| (エ) | 同上 |
【問9】
伊丹さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある妹尾さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>
土地・建物の所在地:東京都△△区○△1-2-3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
土地・建物の所在地:東京都△△区○△1-2-3
取得日:2022年2月17日
取得費:3,500万円
譲渡価額:4,300万円
| 1. | 「2024年10月31日に伊丹さんが家族と共に居住の用に供さなくなった場合、その日から2027年12月31日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできません。」 |
| 2. | 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんの2024年の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、本特例の適用を受けることはできません。」 |
| 3. | 「2024年中に譲渡する場合、譲渡先が伊丹さんの子であるときは、本特例の適用を受けることはできません。」 |
| 4. | 「2024年中に譲渡する場合、伊丹さんが2022年に本特例の適用を受けていたときは、本特例の適用を受けることはできません。」 |
正解:2
| 1. | 正しい記述です。3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡する等の要件を満たさなくてはなりません。 |
| 2. | 3,000万円特別控除の特例の適用を受けるための合計所得金額の要件はありません。 |
| 3. | 正しい記述です。3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと等の要件を満たさなくてはなりません。 |
| 4. | 正しい記述です。3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、売った年、その前年および前々年に、3,000万円特別控除の特例の適用や軽減税率の特例など、一定の特例の適用を受けていないことが要件とされています。 |
【問10】
米田さんは、相続により取得した家を賃貸するに当たり、FPの目黒さんに借家契約の説明を受けた。
借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。


<語群>
1.制限はない
2.公正証書等の書面による
3.公正証書に限る
4.賃貸人に正当事由が認められるときは
5.賃貸人の正当事由の有無にかかわらず
6.期間の定めのない契約とみなされる
7.1年の契約期間とみなされる
8.2年の契約期間とみなされる
1.制限はない
2.公正証書等の書面による
3.公正証書に限る
4.賃貸人に正当事由が認められるときは
5.賃貸人の正当事由の有無にかかわらず
6.期間の定めのない契約とみなされる
7.1年の契約期間とみなされる
8.2年の契約期間とみなされる
正解:2、4、6、1
| (ア) | 定期借家契約は、書面または電磁的記録により締結しなくてはなりません。 |
| (イ) | 普通借家契約において、賃貸人が契約の更新を拒むためには、正当事由が必要とされます。 ちなみに、賃借人が更新を拒む場合、正当事由は不要です。 |
| (ウ) | 普通借家契約において、1年未満の契約期間を設定した場合、期間の定めのない契約とみなされます。 |
| (エ) | 定期借家契約は、自由に契約期間を設定することができます。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| ホーム | 進む> |